「うちの子、なぜこんなに計算が苦手なんだろう?」と悩んでいませんか?
計算が苦手だと、算数全体が嫌いになってしまいますよね。
この記事では、計算が苦手な小学生のための具体的な克服法と教え方のヒントを紹介します。
具体的にこの記事では、計算が苦手な原因を解明し、それを克服するための効果的な学習方法や日常生活での工夫を説明しています。
また、親がどのように子どもをサポートできるか、具体的なアプローチも紹介します。
この記事を読むことで、子どもが計算を得意になり、算数への苦手意識を克服する手助けができますので、ぜひお読みください。
計算が苦手な小学生に共通する「苦手の原因」
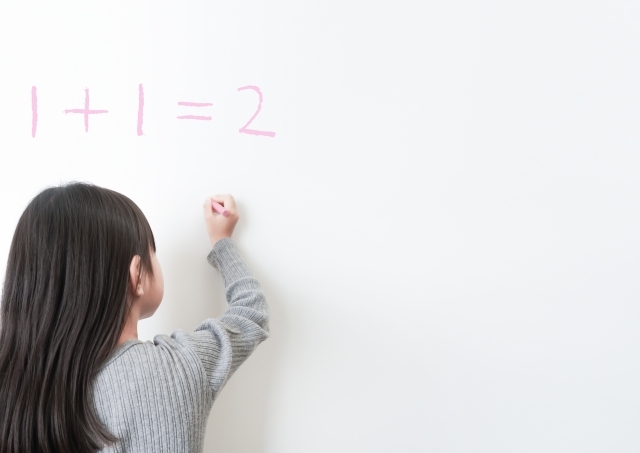
計算が苦手な小学生には、いくつか共通する原因があります。
具体的には、基本的な計算のルールや概念の理解不足が挙げられます。
また、抽象的な概念への理解が不十分であることも考えられます。
算数は抽象的な考え方を求められる教科であり、小学生にとっては難しい部分もあります。
この記事では、これらの原因を具体的に分析し、なぜ計算が苦手になるのかを詳しく説明します。
そして、それぞれの原因に対する効果的な克服方法を紹介しますので、ぜひ読み進めてください。
計算ミスが多い
具体的には、計算ミスの原因として、数字の読み間違いや桁のずれ、計算手順のミスなどが挙げられます。
これらは、基礎的な計算スキルが十分に身についていないことも原因です。
さらに、反復練習が不足していると、計算の精度が上がらず、ミスを繰り返すことになります。
対策としては、まず基礎的な計算のルールや方法を再確認し、確実に理解することが重要です。
また、計算ドリルなどを使って、反復練習を行うことで、計算スキルを向上させることができます。
ケアレスミスが多い
まず、ケアレスミスの原因として、計算を急いで行うことが挙げられます。
早く終わらせたいという焦りから、確認作業を怠りがちになります。
また、計算中に他のことに気を取られやすい子どもは、途中で注意が散漫になり、ミスを犯しやすくなります。
数字の読み間違いや、計算の途中での記述ミスなども、ケアレスミスの一因です。
ケアレスミスを減らすためには、まず計算をゆっくり丁寧に行う習慣をつけることが大切です。
一つ一つの計算を丁寧に確認し、ミスがないかを見直す時間を設けるようにします。
また、計算の過程で途中経過を紙に書き出すことで、どこでミスが発生したのかを特定しやすくなります。
基礎の理解が不十分
基礎の理解が不十分なことは、計算が苦手な小学生に共通する大きな原因です。
基礎がしっかりと身についていないと、複雑な問題に取り組む際にどうしてもつまずいてしまいます。
これにより、計算全般に対する苦手意識が強まり、自信を失うこともあります。
具体的には、基本的な計算ルールや数の概念をしっかりと理解していないことが原因です。
例えば、繰り上がりや繰り下がりの概念が曖昧だったり、四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)の順序が理解できていなかったりします。
また、抽象的な数の概念を具体的にイメージする力が不足している場合もあります。
この問題を克服するためには、簡単な計算問題から始めて、徐々に難易度を上げる段階的な学習方法を取り入れることが効果的です。
抽象的な思考が苦手
抽象的な思考とは、具体的な物や状況を離れて概念や関係性を理解する能力を指します。
これが苦手だと、数や計算の概念を理解するのが難しくなり、複雑な問題を解く際に混乱しやすくなります。
具体的には、抽象的な思考が苦手な子どもは、数の概念や計算の法則を理解するのに時間がかかります。
例えば、掛け算や割り算の意味を具体的にイメージできず、暗記に頼ることが多くなります。
また、文章題や図形問題に取り組む際に、問題の意図を把握するのが難しくなることもあります。
この問題を克服するためには、具体的な物や事例を使って抽象的な概念を教えることが効果的です。
例えば、具体的な物を使って数を数えたり、図や絵を使って計算の過程を視覚化したりする方法が有効です。
自信をなくしている
自信をなくしていることは、計算が苦手な小学生に共通する深刻な問題です。
自信がなくなると、学習に対する意欲も低下し、計算に対する苦手意識がますます強くなります。
これにより、さらに計算ができないという悪循環に陥ってしまいます。
具体的には、計算ミスが続くことで「自分は計算が苦手だ」と感じ、自信を失います。
この問題を克服するためには、まず小さな成功体験を積み重ねることが重要です。
簡単な計算問題から始め、少しずつ難易度を上げていくことで、子どもに成功体験を与えます。
また、親や教師が子どもの努力を認め、具体的に褒めることで自信を取り戻させることが大切です。
計算力アップに必要な基礎固め
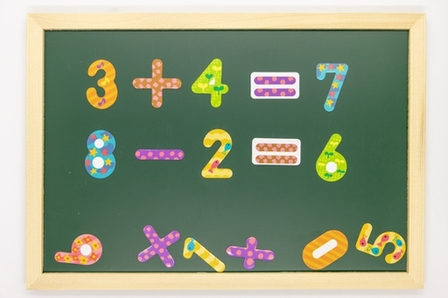
計算が苦手な原因を理解したら、次に重要なのは基礎固めです。
計算力を向上させるためには、基本的な計算のルールや概念をしっかりと身につけることが必要です。
これにより、計算の正確さとスピードが向上し、算数全般に対する自信もつきます。
また、反復練習を行うことで、計算力は着実に向上します。
日常的に計算練習を取り入れることで、子どもが計算に慣れ、自信を持って取り組むことができるようになります。
この記事では、基礎固めの具体的な方法について詳しく説明します。
読むことで、計算力を確実にアップさせるための実践的なアプローチが理解できるので、ぜひお読みください。
基本的な計算練習を繰り返す
基本的な計算練習を繰り返すことは、計算力を向上させるために不可欠です。
具体的には、毎日少しずつでも計算練習を継続することが大切です。
例えば、簡単な足し算や引き算から始め、慣れてきたら掛け算や割り算に進むという段階的な方法が効果的です。
反復練習を行うことで、計算のスピードと正確さが向上します。
また、ドリルや問題集を使って、さまざまな問題に取り組むことも重要です。
計算練習を行う際には、楽しさを取り入れることもポイントです。ゲーム感覚で計算問題に取り組むことで、子どもの興味を引きやすくなります。
計算ルールと法則を理解する
まず、計算ルールとして重要なのは、四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)の順序です。
これを正しく理解していないと、計算結果が正確になりません。
また、掛け算の九九や割り算の基本的な法則を暗記しておくことも大切です。
これらのルールを日々の練習で繰り返し確認することで、確実に身につけることができます。
計算法則については、例えば、分数の計算や小数の計算における具体的な手順を理解することが重要です。
これには、分母を揃える方法や、小数点の位置に注意する方法などがあります。
これらの法則をしっかりと理解することで、より複雑な計算にも対応できるようになります。
段階を追って学習する
段階を追って学習することは、計算力を向上させるための基礎固めにおいて非常に重要です。
突然難しい問題に取り組むのではなく、簡単な問題から始めて徐々に難易度を上げていくことで、子どもは無理なくスキルを身につけることができます。
まず、基本的な計算からスタートし、慣れてきたら、文章題や図形問題などの応用問題に挑戦します。
ここでは、計算だけでなく問題の読み取りや考え方の整理も必要になります。
段階を追って学習することで、子どもは自信を持って問題に取り組むことができ、成功体験を積み重ねることができます。
徹底的に復習する
徹底的に復習することは、計算力を向上させるために非常に重要です。
計算が苦手な小学生にとって、一度学んだ内容をしっかりと復習することで、基礎を確実に身につけることができます。
復習を怠ると、理解が不十分なまま次の内容に進んでしまい、さらに計算が苦手になる可能性があります。
まず、復習の基本として、毎日の学習内容をその日のうちに見直すことが大切です。
宿題や授業で学んだ内容を短時間でも復習することで、記憶が定着しやすくなります。
また、週に一度はまとめて復習する時間を設け、1週間分の学習内容を再確認します。
これにより、理解が曖昧な部分を早期に発見し、補強することができます。
さらに、テストや小テストの結果を元に、間違えた問題や苦手な部分を重点的に復習することも効果的です。
間違えた問題を何度も解き直すことで、同じミスを繰り返さないようになります。
日常生活で身につける計算力

計算力は日々の生活の中で自然に鍛えることができます。
これにより、計算が苦手な子どもも楽しみながらスキルを向上させることができます。
例えば、買い物の際に商品の合計金額を計算させたり、料理の計量を手伝わせることで、計算に対する抵抗感が薄れ、自然と計算力が向上します。
この記事では、日常生活で計算力を鍛えるための具体的な方法を紹介します。
買い物や料理など、日常のさまざまなシーンでどのように計算練習を取り入れるかを詳しく説明します。
読むことで、子どもが計算を楽しく学び、計算力を自然に向上させるための具体的なアイデアが得られるので、ぜひお読みください。
買い物で計算練習をする
実際の生活の中で計算を使う場面を作ることで、子どもは計算の重要性を実感し、楽しみながら練習することができます。
まず、買い物の際に商品の合計金額を計算させる方法があります。
子どもに買い物リストを渡し、商品の値段をメモしながら合計金額を計算させることで、足し算の練習が自然にできます。
さらに、お釣りの計算も効果的です。
商品を購入した後に、いくらのお釣りが返ってくるかを計算させることで、引き算の練習ができます。
また、セールや割引の計算も実践的な学習になります。
例えば、20%引きの商品を購入する際に、割引後の価格を計算させることで、掛け算や割り算の練習ができます。
料理での計量を練習する
レシピを見ながら材料を計量することで、数の概念を具体的に学ぶことができます。
例えば、砂糖を50グラム量る、牛乳を200ミリリットル計るといった具体的な数値を実際に体験することで、計量の重要性と計算の必要性を理解します。
また、分量を半分にする、倍にするなどの練習も行えます。これは、分数や小数の概念を学ぶのに非常に役立ちます。
さらに、時間の計算も重要な要素です。
料理の過程で、例えば「5分間煮る」や「10分間焼く」など、時間を計る練習ができます。これにより、時間の管理や計算に慣れることができます。
料理を通じて、子どもは時間と数の関係を実感しながら学ぶことができます。
効果的な教材の選び方

日常生活での計算練習に加えて、効果的で適切な教材の選び方も重要です。
これにより、子どもが効率よく計算力を向上させることができます。
計算が苦手な小学生でも、適切な方法と教材を使うことで、楽しく学びながらスキルを身につけることができます。
具体的には、まずおすすめの計算ドリルや問題集を使って、基礎的な計算練習を繰り返すことが大切です。
さらに、オンライン教材やアプリを活用することで、子どもが楽しみながら学習できる環境を整えましょう。
これにより、学習のモチベーションが高まり、計算力の向上が期待できます。
この記事では、効果的な学習方法と教材の選び方を詳しく紹介します。
計算ドリルや問題集の選び方
計算ドリルや問題集は、子どもの計算力を向上させるために非常に重要です。
適切な教材を選ぶことで、効果的に学習を進めることができます。
まず、子どものレベルに合ったドリルや問題集を選ぶことが大切です。
簡単すぎると飽きてしまい、難しすぎると挫折感を感じてしまいます。
最初は基礎的な計算問題が中心のドリルから始め、徐々に難易度を上げていく段階的な教材を選ぶとよいでしょう。
次に、視覚的に分かりやすい教材を選ぶことも重要です。
カラーイラストや図表が豊富に使われている教材は、子どもの興味を引きやすく、理解しやすいです。
正しいオンライン教材の活用方法
オンライン教材を使う際には、学習のリズムを整えることが重要です。
毎日決まった時間に取り組む習慣をつけることで、計算練習が日常の一部となり、無理なく継続できます。
また、オンライン教材の利点を最大限に活かすために、オフラインの学習ともバランスを取りながら進めることが推奨されます。
オンライン教材には進捗管理機能が付いていることが多いので、これを活用して子どもの学習状況を把握し、フィードバックを与えることで、学習の質を高めることができます。
タブレットやアプリの利用の注意点
タブレットやアプリを利用することは、計算が苦手な小学生にとって非常に有効な学習方法ですが、正しく利用しないと逆効果になることもあります。
ここでは、タブレットやアプリの利用における注意点を紹介します。
まず、学習時間を管理することが重要です。タブレットやアプリは楽しい要素が多いため、つい長時間使ってしまうことがあります。
次に、適切なコンテンツを選ぶことも重要です。
教育的な内容が含まれているアプリを選び、子どもが楽しみながら学習できるものを選びます。
さらに、親や教師のサポートが欠かせません。
タブレットやアプリに頼りすぎると、子どもが自分で考える力を失う可能性があります。
定期的に子どもの学習状況をチェックし、わからない部分があれば一緒に解決する時間を作ることが大切です。
親ができるサポート方法

次に重要なのは親がどのように子どもをサポートできるかです。
正しいサポートをすることで、子どもは自信を持って学習に取り組むことができます。
まず、計算ミスを責めずに励ますことが大切です。
子どもがミスをしても、その過程を評価し、どこで間違えたのかを一緒に確認する姿勢が必要です。
また、子どもが計算に成功したときには、具体的に褒めてあげることが効果的です。
これにより、子どもの自己肯定感が高まり、さらに挑戦する意欲が湧きます。
ここでは、親ができる具体的なサポート方法を紹介します。子どもの自信を育てる方法、効果的な褒め方や励まし方、予習や復習のサポート方法など、実践的なアプローチを詳しく説明します。
読むことで、親として子どもを効果的にサポートする方法が理解できるので、ぜひお読みください。
子どもの自信を育てる
自信を持つことで、子どもは積極的に学習に取り組むようになり、計算力の向上に繋がります。
まず、子どもの努力を認めて具体的に褒めることが重要です。
例えば、「今日は計算の問題をたくさん解けて偉かったね」や「難しい問題を諦めずに頑張ったね」といった具体的なフィードバックを与えることで、子どもは自分の成長を実感できます。
これにより、自信がつき、さらに学習に対する意欲が高まります。
ミスを責めない
ミスを恐れずに学ぶ環境を作ることで、子どもは安心して学習に取り組むことができます。
ここでは、ミスを責めずに子どもをサポートする方法について詳しく説明します。
まず、ミスをしたときに責めるのではなく、励ましの言葉をかけることが大切です。
例えば、「次はうまくいくよ」「一緒に解決策を考えよう」といった前向きな言葉をかけることで、子どもは安心して再挑戦できます。
これにより、ミスを恐れずに積極的に学ぶ姿勢を育てることができます。
次に、ミスをした原因を一緒に探り、改善点を見つける手助けをすることも重要です。
子どもがどの部分でつまずいたのかを一緒に確認し、解決方法を一緒に考えることで、次回同じミスを繰り返さないようになります。
予習と復習をサポートする
予習と復習をサポートすることは、学習効果を高めるために重要です。
予習によって新しい内容に対する不安を軽減し、復習によって学んだことを確実に定着させることができます。
まず、予習をサポートするためには、子どもが次の日に学ぶ内容を事前に確認する習慣をつけることが大切です。
例えば、教科書の該当ページを一緒に読んだり、簡単な問題を解かせたりすることで、授業での理解がスムーズになります。
これにより、授業中に新しい内容を初めて聞く不安が軽減され、理解度が向上します。
次に、復習をサポートするためには、学んだ内容をその日のうちに見直す習慣をつけることが重要です。
具体的には、授業で解いた問題をもう一度解いてみる、ノートを見返す、親が簡単なテストを作成して確認するなどの方法があります。
定期的に復習することで、学んだ内容が記憶に定着しやすくなります。
実践的な練習方法と成績アップのアプローチ
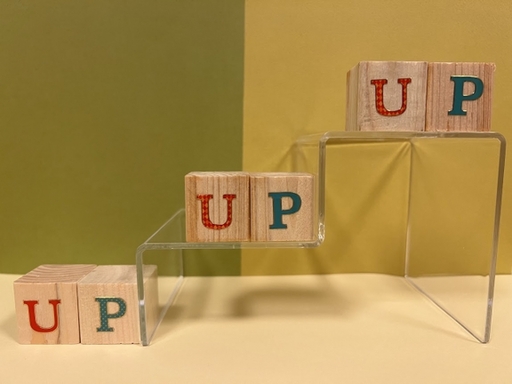
親のサポートが重要であることを理解した上で、次に必要なのは実践的な練習方法と成績アップのための具体的なアプローチです。
効果的な練習方法を取り入れることで、計算力を確実に向上させることができます。
まず、簡単な問題から始めて徐々に難易度を上げていくことが重要です。
これにより、子どもは達成感を感じながら学習を進めることができます。
次に、日々の反復練習を取り入れることで計算スピードと正確さを向上させます。
また、子どもが理解しやすいように、問題を図や具体例を使って説明することも効果的です。
この記事では、実践的な練習方法と成績アップのためのアプローチを紹介します。
具体的な練習ステップ、効果的な教材の活用法、計算力を強化するためのアクティビティなどを詳しく説明します。
読むことで、子どもの成績を確実にアップさせるための実践的な方法が理解できるので、ぜひお読みください。
簡単な問題から始める
まず、基礎的な問題から始めることが重要です。
次に、基礎が固まったら、少しずつ難易度を上げることが大切です。
簡単な問題を解くことで成功体験を積み重ねることができ、子どもが問題を解けるようになると、自信を持って次のステップに進むことができます。
これにより、計算に対する苦手意識が軽減され、学習意欲が高まります。
徐々に難易度を上げる
徐々に難易度を上げることは、計算力を向上させるために効果的なアプローチです。
簡単な問題から始め、少しずつ難しい問題に挑戦することで、子どもは無理なくスキルを伸ばすことができます。
さらに、学習の進捗を確認しながら、必要に応じて復習を取り入れることも重要です。
難易度を上げる際には、前の段階で学んだ内容をしっかりと復習し、理解を深めることで、次のステップにスムーズに進むことができます。
定期的に確認テストを実施し、子どもの理解度をチェックすることも効果的です。
苦手な単元を重点的に練習
特定の単元が理解できていないと、全体的な計算力の向上が妨げられます。
ここでは、苦手な単元を克服するための具体的な練習方法について説明します。
まず、子どもがどの単元を苦手としているかを明確にすることが重要です。
確認テストを行い、どの分野でつまずいているのかを把握します。
例えば、分数の計算が苦手なら、分数の基本的な概念から再確認し、段階的に練習を進めます。
このように、具体的な苦手部分を特定することで、効果的な対策を立てることができます。
次に、苦手な単元に特化した問題集やドリルを活用します。
例えば、分数の計算が苦手な場合は、分数に特化したドリルを使って反復練習を行います。
計算の過程を一つ一つ確認しながら進めることで、理解を深めることができます。
また、視覚的に理解しやすい教材を使うと、抽象的な概念も具体的に捉えやすくなります。
達成感を感じる練習を取り入れる
達成感を感じさせる練習も効果的です。
達成感を得ることで、自信を持ち、さらに学習に取り組む意欲が高まります。
ここでは、子どもに達成感を感じさせる具体的な練習方法について説明します。
まず、目標を設定することが重要です。
目標は大きなものではなく、子どもが達成可能な小さな目標から始めると良いです。
例えば、「今日の計算ドリルを全て正解する」や「5分以内に10問の足し算を解く」といった具体的な目標を設定します。
目標を達成することで、子どもは達成感を感じ、自信を持つことができます。
さらに、練習の過程で進捗を可視化する方法も効果的です。
例えば、毎日取り組んだ問題の数や正解数をグラフにすることで、自分の成長を実感させます。
視覚的に達成感を感じることができるため、モチベーションが維持されやすくなります。
成功体験を積み重ねるためにすること

実践的な練習方法を取り入れたら、次に大切なのは成功体験を積み重ねることです。
成功体験は子どもの自信を育み、学習意欲を高めるために非常に重要です。
これにより、計算が苦手な子でも、楽しみながら学習を続けることができます。
まず、小さな目標を設定し、それを達成することで成功体験を積み重ねる方法が効果的です。
たとえば、毎日の計算ドリルで一定の問題数を正解することを目標にするなど、達成可能な目標を設定します。
次に、達成した際には具体的に褒めてあげることで、子どもの自信を高めます。
この記事では、成功体験を積み重ねるための具体的な方法を紹介します。
小さな目標設定の仕方、達成した際の褒め方、子どもが成功を実感できる具体的なアプローチなどを詳しく説明します。
読むことで、子どもが学習に対してポジティブな意識を持ち、計算力を向上させるための実践的な方法が理解できるので、ぜひお読みください。
成功体験の重要性を知る
まずは「成功体験の重要性を知ること」が大切です。
成功体験を通じて得られる自信と達成感は、学習意欲を高め、計算力の向上に繋がります。
ここでは、成功体験の重要性とその効果について詳しく説明します。
まず、成功体験は子どもの自己肯定感を育てます。
計算の問題を解くたびに成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という自信が芽生えます。
例えば、簡単な問題を解いて正解することができたら、子どもは自分の努力が報われたと感じます。
この自信がさらなる学習への意欲を引き出します。
次に、成功体験はポジティブな学習環境を作ります。
成功することで得られる喜びや満足感は、勉強に対する前向きな態度を育てます。
失敗ばかりだと「どうせできない」というネガティブな気持ちになりがちですが、成功体験があると「次も頑張ろう」というポジティブな思考が生まれます。
これは、子どもが学習に対して積極的に取り組むための大きな動機付けとなります。
また、成功体験を通じて学習の楽しさを実感させることも重要です。
達成可能な目標を設定する
子どもが無理なく達成できる目標を設定することで、成功体験を得やすくなり、自信を持って学習に取り組むことができます。
まず目標は具体的で現実的なものにします。
大きすぎる目標は達成が難しく、逆に自信を失う原因となります。
例えば、「今日の計算ドリルを全部解く」という目標よりも、「今日のドリルのうち、最初の5問を正確に解く」といった具体的で達成可能な目標を設定します。
これにより、子どもは目標を達成する喜びを感じやすくなります。
次に、目標を小さく設定して段階的に進めることが大切です。
一度に大きな目標を設定するのではなく、細かく分けて段階的に達成していく方法です。
このように小さなステップに分け、小さな成功体験を積み重ねることで、子どもは自信をつけることができます。
定期的にフィードバックをする
フィードバックを通じて、子どもは自分の進歩を確認し、自信を深めることができます。
ここでは、効果的なフィードバックの方法について説明します。
まず、フィードバックは具体的であるべきです。
子どもの努力や成果を具体的に指摘することで、何が良かったのかを明確に伝えることができます。
次に、フィードバックのタイミングも重要です。
学習の直後にフィードバックを行うことで、子どもはその場で自分の成果を確認することができます。
また、定期的にフィードバックを行うことで、子どもは継続的に自分の進歩を感じることができます。
例えば、週に一度のペースで進捗を確認し、良い点や改善点を伝えることで、子どものモチベーションを維持することができます。
さらに、ポジティブなフィードバックを心がけることも大切です。
成功体験を親子で共有する
親と一緒に喜びを分かち合うことで、子どもは自分の努力が認められ、さらに頑張ろうという気持ちが育まれます。
子どもが目標を達成したときには、一緒に喜びを共有することが重要です。
さらに、子どもが成功体験を積み重ねる過程を記録し、成長を視覚的に確認できるようにすることも大切です。
親が子どもと一緒に記録を振り返り、「ここまで頑張ったね」と過去の成功体験を一緒に確認することで、子どもはさらなるモチベーションを得ることができます。
計算が苦手な小学生に関するよくある質問集

Q1: 算数が苦手な子どもは発達障害が原因ですか?
A1: 算数が苦手な原因はさまざまですが、発達障害が一因となる場合もあります。発達障害の特性として、注意力の不足や抽象的思考の困難さが挙げられます。これにより、計算や数の概念を理解するのが難しくなることがあります。しかし、必ずしも発達障害が原因とは限りません。まずは専門家に相談し、適切な診断を受けることが大切です。発達障害が原因であっても、適切なサポートと学習法を取り入れることで、算数の苦手を克服することは可能です。
Q2: 計算が苦手な子どもにはどんなドリルがおすすめですか?
A2: 計算が苦手な子どもには、段階的に難易度が上がるドリルがおすすめです。最初は簡単な足し算や引き算から始め、徐々に掛け算や割り算、さらに複雑な問題へと進めるドリルが効果的です。また、ビジュアル的な要素が多く取り入れられたドリルや、ゲーム感覚で学べるドリルも子どもの興味を引きやすいです。
Q3: 計算が苦手な女の子に効果的な克服法はありますか?
A3: 計算が苦手な女の子には、興味を引く教材や方法を使って克服するのが効果的です。例えば、料理やお菓子作りを通じて計量を学ぶことで、計算の実用性を感じてもらう方法があります。さらに、成功体験を積み重ねるために、小さな目標を設定して達成することで自信を持たせることも重要です。
まとめ
この記事では、計算が苦手な小学生のための克服法と教え方について詳しく解説しました。
子どもが計算に対する苦手意識を克服し、自信を持って学べるようになるための具体的な方法やアプローチを紹介しています。
ここでは、記事の内容を簡単に振り返ります。
ポイント:
- 計算が苦手な小学生に共通する原因
- 基礎理解の欠如
- 抽象的思考能力の発達段階
- 自信喪失の影響
- 計算力を向上させるための基礎固め
- 基本的な計算練習の重要性
- 段階的な学習法
- 基礎知識の徹底復習
- 日常生活で身につける計算力
- 買い物での計算練習
- 料理での計量練習
- ゲームや遊びを活用した練習
- 効果的な学習方法と教材の選び方
- おすすめの計算ドリルと問題集
- オンライン教材の活用
- タブレットやアプリの利用
- 親ができるサポート方法
- 子どもの自信を育てる方法
- ミスを責めないアプローチ
- 褒めるタイミングと方法
- 実践的な練習方法と成績アップのアプローチ
- 簡単な問題から始める
- 徐々に難易度を上げる
- 苦手な単元を重点的に練習
- 成功体験を積み重ねるためにすること
- 小さな目標設定と達成
- 継続的なフィードバック
- 算数の楽しさを共有するための工夫
- 算数のゲームやパズルの活用
- 実生活における算数の応用例
この記事を通じて、計算が苦手な小学生が自信を持って学習に取り組めるようになるための方法を理解していただけたと思います。
これらのポイントを参考に、日常生活や学習の中で具体的に実践してみてください。
子どもの成長をサポートし、算数の楽しさを共有することで、計算力を自然に向上させることができます。

算数・数学の個別指導歴15年の鈴木が、算数苦手な生徒さんをサポートします。
「算数の成績を上げたい」「中学入試対策のできる家庭教師を探している」という方は、ぜひ一度ご相談下さい。
