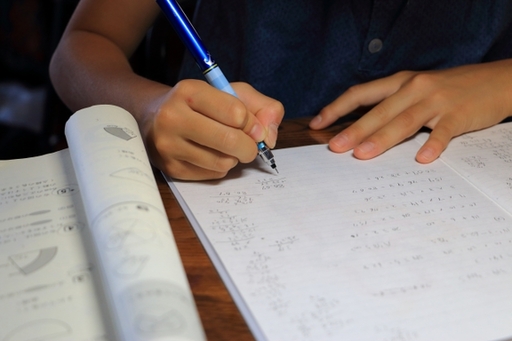中学受験を目指して塾に通っていても、「毎日宿題に追われて終わる」「テストの点数が伸びない」「過去問に手が回らない」といった悩みを抱えるご家庭は少なくありません。
特に、塾から出される大量の宿題やテスト対策に追われて、「自分で解ける力」が身についていないのでは?と不安に感じる親御さんも多いでしょう。
この記事では、「塾の勉強を“こなす”だけで終わらせず、合格に必要な力を着実につけていくためのポイント」について、具体的な方法とともにお伝えします。
宿題を「終わらせること」が目的になっていませんか?
塾の宿題をただ「提出するためにやる」ことが目的になってしまうと、学力はなかなか定着しません。
特に、解説を写すだけの勉強では、「読んだ気」「分かった気」になるだけで、実際に自分の力で問題を解けるようにはなりません。
大切なのは、「解けなかった問題」を放置せず、「どこでつまずいたのか」を自分で言葉にして振り返ることです。
また、解説を写すだけで終わらせず、同じ問題や類題を時間をおいてもう一度解く「反復の機会」を作ることが必要です。
「自力で解けるかどうか」を家庭で確認する工夫を
「解説を見ながらなら解ける」という状態は、まだ「分かった」だけの段階です。受験で必要なのは、「何も見ずに自力で正解できる力」です。
家庭では、次のような工夫をしてみましょう。
- 宿題やテスト直しをしたあとに、数日後「同じ問題をもう一度解かせてみる」
- 「どうやって解いたのか」を口頭で説明させる
- 問題に自分で○×をつけて、どこで間違えたのかを整理させる
こうした取り組みによって、「理解 → 定着 → 自力解答」という流れを家庭でも作ることができます。
テスト対策だけに追われない「過去問演習」の重要性
塾では毎週の確認テストや模試の対策に追われがちで、なかなか過去問に取り組めないという声も多く聞かれます。
しかし、過去問は志望校の出題傾向や難易度を知るうえで、受験勉強の「軸」となるべきものです。
たとえば、6年生の秋以降は、週に1回でもいいので「志望校の過去問に触れる時間」を家庭で確保しましょう。
最初は解けなくても大丈夫。「出題のパターンを知る」「時間配分をつかむ」ことが目的です。
また、過去問は「やりっぱなし」にせず、間違えた問題をピックアップして、類題で再確認することが合格力につながります。
家庭ができるサポートは「量より質」の意識づけ
「毎日どれだけ勉強したか」よりも、「その勉強がどれだけ身についたか」に目を向けましょう。
たとえば、同じ30分でも「分からない問題を3つだけじっくり見直す」方が、「なんとなく10問を終わらせる」よりずっと効果的です。
家庭でできるサポートとしては、
- 宿題のチェックではなく、「解き方の説明を聞く」
- 子どもが「自分の言葉」で説明できるかを確認する
- スケジュールに「見直し」や「解き直し」の時間を確保する
こうした取り組みによって、勉強の「質」を上げる手助けができます。
【まとめ】
中学受験は、「宿題をこなすこと」「テストの点を一時的に上げること」だけでは突破できません。
必要なのは、「分かった」ことを「自力で解ける」に変えていく学びの積み重ねです。
日々の家庭での関わり方を少し見直すだけで、お子さんの学習効果は大きく変わります。