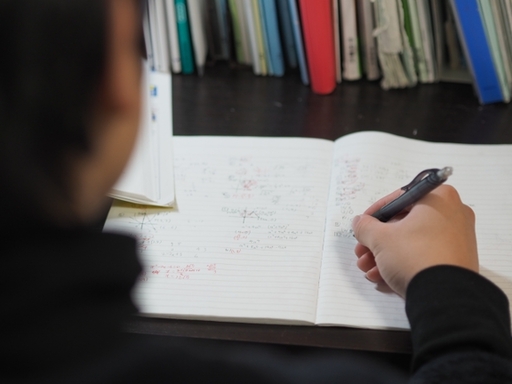中学・高校と進むにつれて「数学が苦手になった」という声は少なくありません。
しかし、その原因の多くは実は「小学生のときの算数の学び方」にあります。
ただ公式を覚えるだけの学習では、やがて複雑な数学につながる「考える力」や「読み解く力」が不足してしまいます。
だからこそ、小学生のうちに「数学につながる学び方」を意識しておくことが大切です。
本記事では、将来の数学につながる基礎力を育てるための算数の勉強法を、具体的に紹介していきます。
どれも今日から実践できる内容ばかりですので、ぜひ参考にしてください。
「量」と「数」の結びつきを意識する
算数では「りんごが3個」や「1個100円」といったように、「数量」と「数値」が結びついて問題が作られます。
この「量(意味のある数字)」と「数(単なる数字)」の違いを理解することで、文章題や応用問題の理解力が大きく変わります。
例えば「100円×3個」は、「1個あたりの量×個数=合計金額」という関係を表しています。
ただの計算練習ではなく、「なぜその式になるのか?」を考える癖をつけることで、数学的な感覚が自然と身についていきます。
「かけ算」か「わり算」かを正確に判断する
「かけ算」と「わり算」の使い分けに迷う子どもは多くいます。
「何倍にするのか?」「いくつ分に分けるのか?」という場面判断ができることは、後の方程式や関数を学ぶ土台となります。
文章題を読むとき、「この数は“1つ分”か、“全体の数”か?」という視点を持ちましょう。
絵や図を使って整理しながら考えると、どちらの計算が適切か自然と見えてきます。
「自分で図形を描くクセ」をつける
図形問題が苦手な子の多くは「図を描かずに考える」傾向があります。
しかし、図形の問題では「目で見て確認する」ことが非常に重要です。
手を動かして図を描くことは、空間認識力や論理的思考力を育てる第一歩です。
「正確な図を描く」「必要な情報を書き込む」「気づいたことに印をつける」など、図を使った思考習慣を身につけるようにしましょう。
「問題文の読み方」を身につけるようにする
「問題文を最後まで読まない」「読み飛ばして解く」などのクセは、学年が上がるほど致命的になります。
数学では、条件を正確に読み取る力が求められるため、小学生のうちにしっかりとした読解力を養うことが大切です。
まずは「誰が、何を、どうしたのか?」を確認するように読んでみましょう。
線を引いたり、メモを書き込んだりしながら読む習慣をつけることで、読み間違いを防ぎ、問題の本質に気づけるようになります。
「見直しの仕方」を身につけるようにする
算数において「見直し」はただの確認作業ではなく、論理的に自分の考えを検証する重要なステップです。
中学以降の数学でも「検算」「逆算」「別解の確認」などが必要になるため、小学生のうちから見直す習慣をつけておきましょう。
見直しの際は「計算だけ合っているか」ではなく、「式の立て方が正しいか」「問題の条件を正しく使っているか」まで確認することがポイントです。
自分のミスのパターンに気づくことで、数学的思考力がさらに伸びていきます。
まとめ
数学の得意・不得意は、実は小学生の算数学習で大きく差がつきます。
「考える」「読み解く」「整理する」といった力を育てることが、将来の数学の理解を助けてくれるのです。
今回紹介した5つの勉強法は、いずれも今日から実践できる基本的なものばかり。
ぜひ日々の学習に取り入れて、「数学に強い子ども」を育てていきましょう。