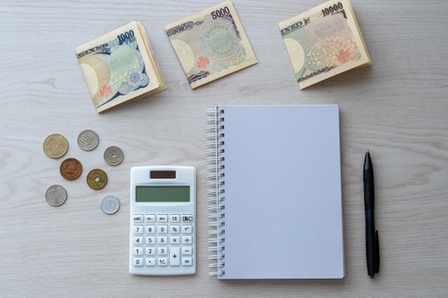中学受験の算数では「つるかめ算」の応用問題として、定価販売と割引販売を組み合わせた文章題が頻出します。
中学の入試問題では、単なる計算だけでなく「利益の仕組み」や「全体の関係」をしっかり捉える力が求められます。
今回は、雙葉中学の実際の過去問を例に、仕入れ値・定価・割引・利益といった条件を整理しながら、つるかめ算で解き進める方法を丁寧に解説します。
ぜひ一緒に手を動かしながら確認してみましょう。
問題文の確認
以下は2024年度の入試問題です。
仕入れ値が110円の商品を217個仕入れ、5割の利益を見込んで定価をつけました。定価で▢個売ったところ、売れなくなったので、定価の2割引きで売りました。全部売り切り、利益は7810円でした。定価で売った個数を求めなさい。
定価と割引価格を求める
仕入れ値が110円、そこに5割の利益をのせるので定価は
110×1.5=165円 となります。
また、定価の2割引きは 165×0.8=132円 です。
つまり、165円で売った商品と132円で売った商品が合計217個あることが分かります。
売上金額の整理
すべて定価で売った場合の売上は
165×217=35805円。
しかし実際には利益が7810円、仕入れ総額は 110×217=23870円 なので、実際の売上は
23870+7810=31680円 です。
つるかめ算で考える
定価販売と割引販売の差は 165-132=33円。
売上が想定より少なくなった分は
35805-31680=4125円。
この差額を33円で割ると
4125÷33=125個 が割引販売された数となります。
したがって、定価で売った数は
217-125=92個 です。
まとめ
今回の雙葉中学の過去問は、仕入れ値・定価・割引・利益を整理しながらつるかめ算で考える応用問題でした。ポイントは、
- 定価と割引価格をまず計算する
- 売上の「想定」と「実際」を比べる
- つるかめ算で個数を求める
という流れです。
中学受験算数では、このように「条件を整理→差を計算→割る」というステップを意識することで、複雑な文章題もスッキリ解けるようになります。