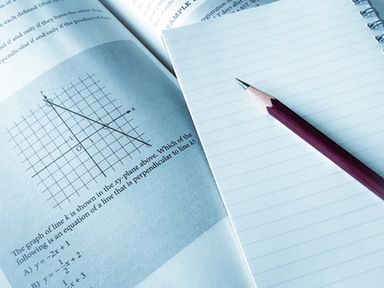算数でよく出題される「平均の速さ」の問題は、一見すると「足して割る」だけで簡単に思えるかもしれません。
しかし実際には、「移動した距離の合計 ÷ 移動時間の合計」で求めなければならず、勘違いしやすい単元のひとつです。
特に「速さの平均」と「数値の平均」を混同してしまうケースが多く、入試やテストで失点する子も少なくありません。
この記事では、実際の入試レベルの例題を使って「平均の速さの求め方」をわかりやすく解説するとともに、つまずきやすい誤りについても紹介します。
平均の速さの基本的な考え方
「平均の速さ」とは、全体でどれだけ進んだか ÷ 全体でどれだけ時間がかかったか で求めるものです。
速さが途中で変わっても、「トータルの距離」と「トータルの時間」さえ分かれば必ず計算できます。
たとえば、A君が時速5kmで2時間、時速3kmで3時間歩いた場合、それぞれの移動距離は10kmと9kmで合計19km。
時間は合計5時間なので、平均の速さは 19÷5=3.8km/時 となります。
間違えやすいポイント
平均の速さの問題で多い間違いは、与えられた速さの数値を単純に平均してしまうことです。
この問題でも「(5+3)÷2=4」としてしまうケースがよくあります。
しかし、実際には移動時間や距離が異なるため、ただの数値の平均は意味を持ちません。
「必ず距離と時間を使って計算する」 というルールを押さえておきましょう。
入試での応用力をつけるには?
入試では「行きは時速x km、帰りは時速y kmで移動したときの平均の速さを求めよ」といったパターンもよく出ます。
こうした場合は「往復の距離」と「往復にかかった時間」をそれぞれ求め、最後に割り算をすることが大切です。
まずは基礎の考え方=距離÷時間を徹底して身につけておくと安心です。
よくある質問集
Q1. 平均の速さと普通の平均の違いは何ですか?
A. 普通の平均は「数値の合計 ÷ 個数」で求めますが、平均の速さは「距離 ÷ 時間」で求めるものです。速さは「時間と距離の関係」で決まるため、単純な数値の平均では意味がありません。
Q2. 行きと帰りで速さが違う場合、必ず調和平均を使うのですか?
A. 調和平均は便利な公式ですが、無理に覚える必要はありません。基本に立ち返り、「行きの距離と時間」「帰りの距離と時間」をそれぞれ求め、合計したうえで距離÷時間をすれば必ず答えは出せます。
Q3. 入試問題で速さの平均が出たら、まず何を考えればいいですか?
A. まず「移動距離の合計」と「かかった時間の合計」を計算することを意識しましょう。そのあとに割り算をする、という手順を徹底するとケアレスミスを防げます。
まとめ
平均の速さは「移動距離の合計 ÷ 移動時間の合計」で求めることが基本ルールです。
単純に速さの数値を平均してしまうと誤答になりやすいため注意が必要です。
入試では、往復問題や区間ごとに速さが異なるケースが多く出題されますが、どんな場合でも「距離」と「時間」を合計すれば必ず答えが出せます。
まずは基礎的な計算に慣れ、そこから応用問題へとステップアップしていきましょう。