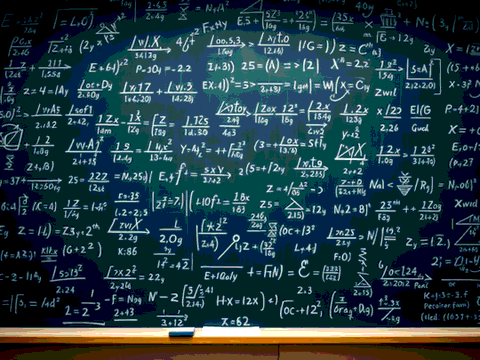MARCH(明治・青山・立教・中央・法政)の付属高校を目指す受験生にとって、数学は「合否を分ける科目」です。
英語や国語で差がつきにくい一方、数学ではわずか10点の差が順位を大きく変えるのが現実。
「模試で偏差値60前後から抜け出せない」「あと一歩届かない」という受験生でも、正しい勉強法と戦略を取れば、偏差値70の壁を突破できます。
この記事では、MARCH付属校の数学出題傾向と、逆転合格に必要なステップを具体的に解説します。
MARCH付属高校の数学の出題傾向と特徴
基礎~標準問題中心だが、思考力が試される
MARCH付属高校(明大中野・青山学院・立教新座・中央大杉並・法政二など)は、教科書レベル+αの「考えさせる」問題を多く出題します。
基本的な知識をベースに、どれだけ柔軟に応用できるかが勝負です。
特に多いのは以下の出題タイプです。
- 関数と図形の融合問題
- 場合の数・確率の条件付き問題
- 方程式・不等式の文章題
- 計算力+論理力を要する整数問題
難問よりも「取りこぼさない力」が重要
他の最難関校のような超難問は少なく、標準問題を確実に得点する力がカギ。
「解けるはずの問題を落とさない」ことが、偏差値70への最短ルートです。
偏差値60→70に伸ばす3ステップ勉強法
「基礎問題で満点を取る力」を身につける
偏差値60台前半の受験生は、まだ「基礎の精度」にムラがあります。
たとえば、
- 式変形の途中で符号ミス
- 図形の条件を見落とす
- 方程式の処理で時間を使いすぎる
こうした小さなミスの積み重ねが10点以上の差を生みます。
基礎問題集(例:『体系数学』『新中問』『チャート式中学』)を使い、「解法の流れを正確に再現できるか」を徹底的に練習しましょう。
「思考系問題」を毎日1問解く
MARCH付属高の数学は、一見難しく見えても、筋道を立てれば解ける問題が多いです。
つまり「パターン暗記型」よりも、「考える練習」が圧倒的に重要です。
おすすめは次の方法です:
- 問題を見て、まず自分の言葉で条件を整理する
- 解答を見ずに、5分間「考える過程」をノートに書く
- 解説を読んで、“どこで発想がずれたか”を分析
この「思考の記録」を残すことで、応用問題にも対応できる力がつきます。
使うべき教材・問題集リスト
| レベル | 教材名 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 基礎固め | 新中学問題集・体系数学・チャート式中学 | 計算・基本公式の徹底 |
| 応用練習 | 入試標準問題集・駿台模試過去問 | 思考力・応用力の強化 |
| 実戦演習 | 志望校過去問 | 時間配分・答案作成力 |
ポイント:教材を増やしすぎず、「同じ教材を3回解く」方が得点力は上がります。
模試の活用と復習法
模試を「点数の確認」だけで終わらせるのはNGです。
偏差値を10上げたいなら、「間違いノート」を作りましょう。
間違いノートに書くべき3項目
- どんなミスをしたか(計算・条件・思考)
- どう考えれば正解にたどり着けたか
- 次に同じ問題が出たらどうするか
この記録を積み重ねることで、「同じ失敗を繰り返さない力」が身につきます。
家庭でできるサポート(保護者向け)
- 「結果」ではなく「思考の過程」を褒める
- 「どうしてそう考えたの?」と問い返す
- 一緒に“間違いノート”を見て進捗を共有する
特に中3秋以降は、精神的にも焦りが出やすい時期。
親が冷静にペースを整えてあげることで、最後までモチベーションを維持できます。
直前期の戦略
取れる問題を確実に取る
難問挑戦よりも、標準問題で確実に8割取る練習を。
試験中に「これなら解ける」と感じる問題を最優先に解くことが、合格点への最短ルートです。
模試・過去問の「解き直し」が最強の勉強
直前期の1問=新しい問題を解くよりも、過去に間違えた問題を完全に理解する方が効果があります。
よくある質問
Q1. MARCH付属校は難関校と比べてどのくらいのレベル?
→ 一部は偏差値70前後に位置し、都立トップ校と同レベル。
数学は「処理速度+論理整理力」で差がつきます。
Q2. 過去問はいつから始めればいい?
→ 中3の夏以降が目安。秋からは“本番時間で解く”練習を。
Q3. 塾に行かなくても合格できますか?
→ 独学でも可能ですが、志望校の出題傾向を知る指導者がいると効率が格段に上がります。
まとめ
MARCH付属高校で数学偏差値60→70を目指すには、
- 基礎を速く・正確に
- 思考系問題で発想力を磨く
- 過去問で得点戦略を立てる
という3ステップが不可欠です。
「あと10点上げる勉強」ではなく、“確実に取る力”を積み上げる勉強が、逆転合格への鍵となります。