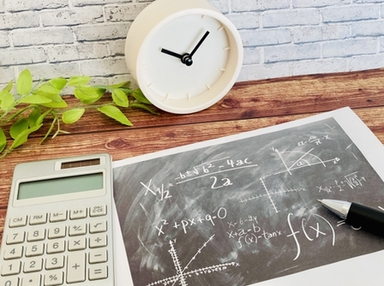中学受験の算数において、グラフ問題(速さ・割合・水量・点の移動・規則性)は毎年必ずのように出題される重要単元です。
ところが、塾でも学校でも「とりあえず読み取り練習」「とりあえず問題演習」で済まされてしまい、本質の理解ができないまま苦手になる子が続出します。
しかし安心してください。
グラフ問題を得意にするには、特別な才能は不要です。
“正しい考え方”と“図・表・線の書き方”を身に付けることで、偏差値40台からでも確実に伸ばせます。
この記事では、
✔ グラフ問題が苦手になる理由
✔ グラフ問題を得意にするための具体的な勉強法
✔ 家庭で取り組める練習メニュー
✔ 保護者の方ができるサポート
まで完璧にまとめます。
中学受験で出るグラフ問題の種類を知る【まずは全体像】
グラフ問題は種類によって考え方がまったく異なります。
まずは「どんなタイプがあるか」を整理しておくことが大事です。
① 速さのグラフ(距離‐時間グラフ)
最も頻出。読解・作図・瞬間の速さ・出会い・追い越しなど幅広い。
② 水槽と水量のグラフ
入る・出る・止める・混ぜる・高さの変化など、規則性と融合しやすい。
③ 変化の割合・割合グラフ
割合の変化、濃度、単位量あたりなどと絡むタイプ。
④ 点の移動(位置グラフ)
立体図形・平面図形と合わせて出されることも多い。
⑤ 規則性と結びつくグラフ
周期性・繰り返し・折れ線の意味を読み取る問題。
まずは「どれが得意でどれが苦手か」を把握するだけで対策が一気に進みます。
グラフ問題が苦手な子が共通してつまずく3つのポイント
① “軸の意味”を理解していない
・横軸が時間なのか距離なのか
・縦軸が水量なのか高さなのか
ここが曖昧だと、どれだけ練習しても上達しません。
② グラフを読んでいるのではなく「眺めているだけ」
グラフの折れ曲がりや傾きの意味を読み取れないと、問題文の状況を復元できません。
③ 自分でグラフが書けない
「読むことはできても書けない」子は本質が身についていません。
“書ければ強い”のがグラフ問題です。
グラフ問題を得意にするための勉強法【核心部分】
① まずは文章から「時間・量・速さ」を抜き出す練習
問題文を読んだら、
・どの量が変化するのか
・その変化は速いのか遅いのか
・増えるのか減るのか
を必ずメモして整理します。
✔ 重要:数値を線でつなぐ前に“言葉で整理”
これだけで正答率が劇的に上がります。
② 「グラフを自分で書く」練習を必ず行う
グラフ問題が得意な子は、例外なく“作図がうまい”です。
家庭学習では以下を徹底してください。
◎ 練習手順
- 横軸と縦軸のラベルを書く
- 主な時刻・量を点で打つ
- 点を結ぶ前に「増加」「減少」「一定」の確認
- 最後に直線で結んで完成
「雑に書く→読めない→ミスる」の悪循環を断ち切ることができます。
③ 「傾き」の理解を徹底させる
距離‐時間グラフの傾き=速さ
水量グラフの傾き=水の増え方(注水量)、水の深さなど
これが腑に落ちると、一気に世界が変わります。
④ 逆向きのグラフ・折れ線の意味を説明できるようにする
・折れ曲がった理由
・横軸に平行 → とまっている
・縦軸に平行 → 一瞬で変化(ありえない=書き方ミス)
この「言葉で説明できる力」が、偏差値60以上の子の共通点です。
⑤ グラフを「文章化・言語化」する習慣をつける
グラフを見たら、「今どんな動き?」「何が増えて何が減ってる?」と必ず説明する。
文章化できる=理解が定着している証拠。
家庭でできる!グラフ問題の練習メニュー3選
① 毎日1問「短時間グラフ」練習
・小問形式
・読取り中心
・5分程度でOK
毎日続けると、感覚が研ぎ澄まされます。
② 過去問の「グラフ問題だけ抜き出し」演習
大問全部をやる必要はありません。
まずは
✔ グラフ
✔ 図形
✔ 速さ
のように分野別で固める方法が効果的です。
③ 白紙から「文章→グラフ」を書く練習
文章を渡して、
「この状況をグラフにしてみよう」
と書かせると、理解度が一気に上がります。
保護者の方ができるサポート
① 子どもが書いたグラフが“丁寧か”をチェック
読み取れないほど雑に書いていないか。
「ていねいさ」だけで正答率は20〜30%上がります。
② 解けないときは“どこを読み違えたか”を一緒に確認
・軸の設定ミス
・点の位置ミス
・増減の向きの勘違い
原因を見つけてあげるだけで、つまずきが取れます。
③ 作図練習の声かけだけでOK
難しいことを教える必要はありません。
「軸は書いた?」
「増えてる?減ってる?」
「折れ曲がった理由は?」
これだけで十分サポートできます。
よくある質問
Q1:グラフ問題はいつから本格的に取り組むべき?
小4後半〜小5がベスト。ただし「読取りの基礎」は小3からでも始められます。
Q2:図形が苦手だとグラフも苦手になりますか?
完全には連動しませんが、図を描く習慣がない子はグラフも苦手になりがちです。作図力を育てるのが先決です。
Q3:過去問より先にやるべき教材はありますか?
はい。「塾のテキスト・例題・練習問題」→「分野別問題集」→「過去問」
の順がおすすめです。
まとめ|グラフ問題は“書いて・読んで・説明する”の3ステップで必ず得意になる
中学受験の算数におけるグラフ問題は、「イメージ力 × 作図力 × 読解力」 の総合問題です。
しかし、特別な才能は不要。
次の3つを徹底すれば、どんな子でも伸びます。
✔ ① 言葉で状況整理
✔ ② 自分でグラフを書けるようにする
✔ ③ 読んだグラフを説明できるようにする
この流れを徹底すれば、偏差値40台→50台→60台へと着実にレベルアップします。