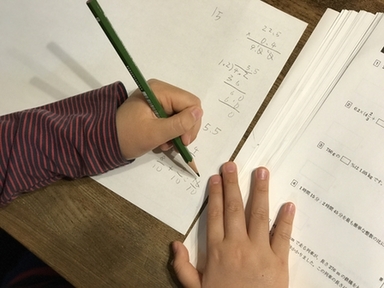中学受験の算数では、「図を描くこと」が正解への大きな一歩となります。
複雑な条件や文章問題でも、自分で図を描くことで情報を整理でき、思考が進みやすくなるからです。
しかし、ただ図を描けばいいというわけではありません。
「描き方」や「描いた後の活用法」によって、解ける問題とそうでない問題がはっきり分かれることもあります。
この記事では、「図を描いて考えるとき」に押さえておきたいポイントと、ありがちな注意点について、受験生や保護者の方に向けて分かりやすく解説します。
まずは正確な図を描き写す
問題文にある図を適当に描いてしまうと、角度や長さのイメージがずれてしまい、間違った解釈をする原因になります。
特に「等しい長さ」「垂直」「平行」といった条件は、図にきちんと反映させることが大切です。
まずは問題文にある図を丁寧にノートへ写し、必要があれば定規やコンパスを使ってできるだけ正確に描きましょう。
「雑な図」が原因で間違えることを防ぐだけで、正答率がぐんと上がることも少なくありません。
描いた図に数字を書き込む
図を描いたら、次にすべきことは「情報の書き込み」です。
長さや角度、割合、個数など、問題文に出てくる数値を図の中にどんどん書き込んでいきましょう。
こうすることで、目に見える形で情報が整理され、どの数字がどこに対応しているのかが一目で分かるようになります。
この「視覚的な整理」が、思考の手助けになり、ミスの防止にもつながります。
「どこに注目するのか」を正しく学ぶ
図を描いても、それをどう見て考えるかが非常に重要です。
たとえば、相似な三角形が隠れていないか、対角線を引くと面積が分かりやすくなるかなど、「注目ポイント」に気づけるかどうかが勝負の分かれ目になります。
塾や家庭学習では、「なぜそこに補助線を引いたのか」「なぜその部分を比べたのか」をセットで学ぶようにしましょう。
思考のパターンを覚えることで、初めての問題にも対応できる力が身につきます。
「思い込み」をしないように注意する
図を描いていると、「なんとなくこの長さは等しそう」「この線はたぶん垂直だろう」といった“思い込み”をしてしまうことがあります。
しかし、問題文に書かれていないことを勝手に想像で補ってしまうと、誤った前提で考えてしまい、正解から遠ざかってしまいます。
図から感じたことが「本当に問題文に書かれているか?」を常に確認しながら進めることが大切です。
「書いてないことは決めつけない」という姿勢が、正確な判断力を育てます。
まとめ
図を描くことは、算数の文章問題を解く上で欠かせない手法です。
しかし、「正確に描く」「数字を整理する」「注目点を見つける」「思い込みをしない」といった一つひとつの丁寧な積み重ねがあってこそ、図は真の力を発揮します。
日頃から、図の描き方や見方を意識して練習しておくことで、どんな問題にも落ち着いて対応できるようになります。
図を味方につけて、算数の得点力をぐっと高めていきましょう。