お子様の算数の成績が気になりませんか?
また、お子様が算数が苦手だと感じている場合、どのように教えれば良いのかでお悩みではありませんか?
この記事では、算数を教えられない親御さんのために、お子様が抱える苦手意識を克服するための教え方をご紹介します。
結論から言うと、お子様の学力や目標に合わせたわかりやすい指導が必要です。
この記事をお読みいただくことで、お子様の算数の力を伸ばすためのヒントを得ることができます。
算数の力が身につくだけではなく、お子様とのコミュニケーションが深まり、親子関係も良好になることで、お子様の自信がつき、学業全体に対するやる気につながることなども期待できます。
この記事を参考にお子様と共に算数を楽しく学び、苦手意識を克服しましょう!
算数が苦手だった親御さんでも大丈夫!子供の苦手を克服する教え方とは?

親御さんにとって、お子様自身が「算数をできるようにするための教え方」を身につけることは難しい課題です。
しかし、算数が苦手だった親御さんでも、お子様の苦手意識を克服するための「適切な教え方」「声のかけ方」を実践することは可能です。
この記事では、算数が苦手だった親御さんでも実践できるような「お子様の苦手意識を克服する教え方」について詳しく紹介します。
具体的には「算数を苦手とする原因」や「適切なアプローチの仕方」「効果的な教材の紹介」など、幅広い情報をお届けします。
このパートを読むことで、算数が苦手だった親御さんでも、お子様の算数の力を伸ばすために必要な知識を得ることができます。
また、お子様が算数に苦手意識を持っている場合には、親御さん自身が「お子様への関わり方」「声のかけ方」を変えることで、お子様の自信を取り戻すことができます。
是非この記事をお読みいただき、お子様が「算数の苦手意識を克服できるような教え方」を実践してみて下さい。
まずは質問を投げかけて「理解できていること」を引き出す
結論からいうとまず大事なのは、算数は「教えなくても良い」ということです。
というのも、お子様にとって「教えられても分からない原因」の一つとして「教える人の知識」と「お子様の中にある知識」とが、合致しないことが挙げられるからです。
例えば「みかんを3個ずつ、5人に配るとき、みかんは全部でいくついりますか?」という問題があるとします。
このとき、大人は「かけ算でできる」と思っても、お子様自身「かけ算」を知らなかったら、「これはかけ算でできるよ!」と教えても、お子様にとっては何のことか分からないですよね。
このような状況下において、まず教える人に求められるのは「みかん3個、誰にあげる?」「みかんをあげたところを絵に描ける?」「絵に描いたみかん全部でいくつある?」などの質問を通して「この子はこの問題を、そもそもどのように考えようとしていたのか」を知ることです。
そうすることで、お子様の中にある知識や考え方を引き出すことができ、結果として「この子はここまで理解できている」ということが分かります。
このプロセスを経て、「それならこの子はこれも理解できる」という希望が見えてきてようやく「これを理解してもらうにはどうすれば良いのか」を考えることができます。
学んでいる内容に合わせた教え方をする
「教え方」と書いてありますが、結果としてこれは「お子さんへの関わり方」「声のかけ方」「質問の仕方」というものに帰着されます。
まずは「お子様の中にある知識・ものの考え方」を引き出した上で、「今学校や塾ではどのような内容を学んでいるのか」「どのように学んでいるのか」を把握することが大事です。
「お子様の現時点での学力レベル」や「お子様の学習目標」に応じて、「やるべき内容や学ぶ順序」を把握した上で「理解してもらえるような声のかけ方・質問の方法」を工夫してみて下さい。
教え方 (声のかけ方など) を工夫するコツとしては、以下のような考えがあります。
- 具体化:これから学ぶことの理解度を高めるために、今までに習ってきたこととの間にある関連性を重視し、具体的な実例や「お子様の中でイメージしやすいもの」を思い出してもらう。
- 振り返り:定着度 (似たような問題が出てきたときに正解を出せる力) を高めるために「そもそもこの問題の正解を出せるきっかけとなった考え方」を振り返る。
- 反復:上のような意味での「振り返り」を経て、「同じ考え方を使って正解できる問題」を何度も繰り返し復習し、解説などを見ないで正解できるようにする。
「数字・量・かたち」に触れる機会を増やす
数字や量、形に触れることは、お子様の算数の学力を高める上で非常に重要なことです。
親御さんはお子様に対して、様々な場面で「数字や量、形が実際に存在していること」に気付いてもらうことが必要です。
たとえば、買い物に行ったときにお金の計算をしてみたり、簡単な計量カップを使って調味料を量ったりすることで比の考え方を身につけたり、身の回りのものを観察して形を学ぶことができます。
お子様と一緒に楽しんで学べる遊びや工作を取り入れることもおすすめです。
これらの方法を通じて、お子様は数字や量、形に対する興味や理解を深め、算数だけではなくその先の数学にも必要な力を習得することができます。
親御さんが知らないことは一緒に調べる
親御さんがお子様に算数を教えるとき、知らないことが出てきてしまうことはよくあります。
しかし、それをお子様に隠してしまうのではなく、一緒に調べることが大切です。
一緒に教科書や参考書を見ながら調べることで、お子様に「親も分からないことがある」ということを教えることができます。
また、一緒に調べることで、お子様が自分で考え、学ぶ姿勢を育てることができます。
親御さんが知らないことを一緒に調べることで、お子様と一緒に学ぶ楽しさや知識の広がりを感じることができます。
親子で学び合うことで、お子様の学ぶ意欲や好奇心を育てることができます。
楽しく学べる環境を作る
算数は難しいと感じることが多いですが、楽しく学べる環境を作ることが大切です。
お子様と一緒に算数の問題を解く時間を作り、解き方を教えるだけではなく、「できていることを具体的に伝えること」が大切です。
こういった取り組みによって楽しく学べる環境を作ることで、お子様が算数に興味を持ち、自然と学習意欲が高まるように工夫しましょう。
ポジティブな言葉かけを心掛ける
算数が苦手なお子様に対して、ポジティブな言葉かけは非常に大切です。
解き方が分からなかったときに、「間違えても大丈夫、次はできるようになるから一緒に頑張ろう!」などの励ましの言葉をかけることで、お子様は自信を取り戻し、楽しく学ぶことができます。
親御さんも、お子様の頑張りや成長に対して「よくできたね!」「努力をしているね!」などの肯定的な言葉かけをすることで、お子様のやる気を引き出すことができます。
教材選びに工夫をする
算数の勉強において、お子様の学力や目標に適した教材を選ぶことは、お子様の学習効果に大きく影響します。
一般的な学校の教材だけでなく、書店やネットで手に入る様々な教材を活用することも大切です。
教材選びのポイントは「お子様の目標や学力に合わせたものを選ぶこと」「お子様が自分一人でも勉強できるような内容を含んでいること」「例題と類題がセットで載っているものを選ぶこと」などです。
また、教材を選ぶ際にはお子様も一緒に考えることも大切で、お子様自身が「これがやりたい!」と思える教材を選ぶことで、学習意欲も高まります。
以下の記事でも、教材の選び方について書いていますので、参考にして下さい。
子どもを算数嫌いにしないために気を付けるべき親の教え方とは?

算数が苦手になってしまうと、学校生活や将来に大きな影響を与えてしまいます。
そこで、親御さんはお子様の算数学習に対して「お子様が算数を嫌いにならないような態度」で関わる必要性があります。
このパートでは、お子様を算数嫌いにしないために気を付けるポイントと、そのポイントを反映した教え方について解説します。
具体的には「どのような言葉をかけるか」「どのように問題に取り組むか」などを紹介します。
このパートを読むことで、お子様が算数嫌いになってしまう原因や、その対処法がわかります。
算数が苦手でも大丈夫ですので、この記事を参考にお子様へのサポート方法を実践して下さい。
親が「算数は面倒くさい」と言わないようにする
実際に私が今まで見てきた親御さんで「算数は面倒くさい」と口にしていた方がいました。
残念ながらその方のお子様は「宿題の答を見る」「勉強したフリをする」というようなことしかしませんでした。
「面倒くさい」と堂々とお子様に対して口にしてしまうことは、「算数がつまらない」「とりあえず勉強したことにさえすれば良い」という考えを助長してしまいます。
ですのでこれとは対照的に、親御さんがお子様に対して算数に対する興味や関心を示すことが大切です。
例えば、日常生活の中に算数に関連したものがないかどうかを話し合ったり、ものの個数や時間の計算などの実践的な例を見せたりすることで、算数が身近なものであることを伝えることができます。
また、お子様が算数の学習に苦手意識を持ってしまった場合には、お子様を叱責したり、責めたりするのではなく、一緒に解決策を見つけることが大切です。
親御さんご自身も算数に対して「面白いと思う気持ち」を持ち、お子様と一緒に楽しく学ぶことが、算数嫌いになることを防止することに繋がります。
プレッシャーをかけずに子どものペースに合わせる
お子様の理解度に合わせて「周りの子と比べずに学習を進めること」は、お子様の学習意欲を高めるために非常に重要です。
特に算数の学習においては、新しく学ぶ単元が出てくるたびに、お子様が理解するまで時間をかけて勉強を進める必要があります。
「周りの子はここまでやっている」というような焦りを、親御さん自身も感じさせないようにすることが大事です。
お子様のペースに合わせて学習を進めることで、お子様は、自分が納得して理解できるまで学習に取り組むことができます。
理解度に合わせて問題演習させてみる
算数の学習においては、練習問題を解くことが大切ですが、問題が難しすぎるとお子様のやる気をそがれてしまいます。
逆に簡単すぎる問題だと飽きてしまい、学習効果が得られなくなります。
お子様の理解度や興味に合わせた適切な難易度の問題を選ぶことで、お子様は効果的な学習ができます。
最も効果的なのは、お子様にとって「少し難しそうだけどできる気がする」という問題を、実際にできるまで見守ることです。
親御さんがプレッシャーをかけずにお子様のペースに合わせることで、お子様は自己肯定感を高め、学習意欲が向上し、結果的に算数に対する興味や好奇心も育まれます。
算数の勉強に適した環境を整える
算数の勉強に適した環境を整えることは、お子様が効果的に学習するために重要です。
勉強しやすい環境を整えることで、子どもたちは集中力を高め、より効率的に学ぶことができます。
一般的には勉強に集中できるよう、静かで明るい場所を選ぶこと、周囲の騒音が少ない場所で勉強できることが望ましいです。
また、お子様が「椅子に座るのが良いのか」「床や畳に直接座った方が良いのか」という考え方も重要です。
結局のところ大事なのは「お子様がどのような環境下であれば勉強に集中できるのか」を明確にすることです。
もし「椅子と机でしか集中できない」ということであれば、机と椅子の高さをお子様の姿勢に適した高さに保ち、長時間の学習にも耐えられるようにする工夫なども大事なことです。
また、算数の勉強に必要な教材や道具を整えることも大切です。
定規、コンパスなどの測定器具や、ノート、テキスト、問題集などの教材を手に届きやすい場所に用意しておくと良いでしょう。
必要なものがすぐに手に入るよう、整理整頓された環境を作りましょう。
親御さんは勉強場所を提供するだけでなく、お子様が質問や疑問を持ったときには、お子様が自分で答を出せるようにするために、一緒に考える姿勢も大切です。
親御さんがお子様の勉強に興味を持ち、サポートすることで、お子様は算数の勉強に熱心に取り組むことができます。
楽しく学べる方法を取り入れる
算数を楽しく学ぶことができる方法についても実践してみる価値はあります。
例えば、数に関するゲームを取り入れたり、実際の生活における数のやりとりを取り上げたりすることが挙げられます。
また、動画やアニメーションなどの映像教材を使用することで、お子様が図形を描くのが苦手だったとしても、まずは図形の描き方や動き方のイメージを、より身近に感じることができます。
さらに、自分で問題を考えたり、実際に体験することで算数に対する興味を持つことができます。
楽しみながら学ぶことで、子どもたちが算数を嫌いにならずに、むしろ興味を持って学ぶことができるでしょう。
家族全員で協力して算数を学ぶ
家族で協力して勉強する環境を作ることは、お子様の学習にとって非常に重要です。
家族が協力し合って勉強することで、子どもは自信を持って学習に取り組むことができ、成績向上につながることもあります。
まずは、家族が共通の勉強時間を設けることが大切です。
毎日決まった時間に勉強する習慣を身につけることで、子どもは勉強の重要性を認識し、やる気が湧いてくることでしょう。
お子様が分からない問題があった場合には、家族が一緒に解決策を考えることで、家族で勉強したことを共有でき、お子様がより深く学びを理解し、知識を定着させることができます。
雰囲気や場所にも気を配り、明るく快適な環境を整えることで、お子様がリラックスして勉強することができます。
家族で協力し合って勉強することで、お子様が楽しく学び、自信を持って成長できるように支援することが大事です。
算数は受験必修科目!親が知っておくべき大切なポイントとは?

算数は、小学校から中学校、高校と進学する上で欠かせない科目の一つです。
受験や将来の進路に関わる重要な科目だけに、親御さんはお子様の算数学習をしっかりと見守り、サポートすることが求められます。
このパートでは、受験必修科目である算数について、親御さんが知っておくべき大切なポイントを解説します。
このパートを読むことで、算数の受験勉強についての重要性や、受験に必要な基礎知識を獲得することができます。
また、お子様の算数学習について理解を深め、適切なサポートができるようになることでしょう。
受験科目としての算数の重要性とは?
算数は、小学校から高校までの学校教育において必修科目であり、大学受験や就職試験などでも頻繁に出題されます。
そのため、お子様が算数に苦手意識を持ってしまうと、受験において大きなハンディキャップとなります。
また、算数の問題を解き「自ら正解を出せる力」は、論理的思考力や問題解決力を養うのにも役立ちます。
そのため、受験科目としてだけでなく、日常生活でも役立つスキルを身につけることができます。
適切な教育方法や教材を選び、お子様が算数に対して苦手意識をなくせるような取り組みが重要です。
中学受験のために学ぶ算数の内容とポイント
中学受験のために学ぶ算数の内容とポイントについてお答えします。
どの偏差値帯の中学を受けるかにもよりますが、中学受験の算数は主に「小学6年間で習う算数の各単元の融合問題」「中学・高校数学の先取り学習」の2つをメインテーマとして学習していくことになります。
例えば問題文の中に「~%」と書いてあったら、一見「割合」の問題だと捉えられますが、中学受験の算数では「割合を比の値と見て、線分図を描いて解く」という方法で正解することが求められます。
この他、中学数学の先取りとしては「図形の合同と相似」、高校数学の先取りとしては「数列と規則性」の問題などが挙げられます。
以下に、中学受験のために必要な算数の内容を、一部紹介します。
- 平面図形 (角度を求めるときに、二等辺三角形を探すことなどが典型的な考え方)
- 立体図形 (難しいイメージがありますが、「立方体の切断」などの定番問題を解けるようにすることが大事)
- 速さとつるかめ算 (「途中まで分速40ⅿ、途中からは分速60ⅿで進んだら合計で20分かかった」などの文章があれば、進んだ道のりを面積で表現する方法が典型的な考え方)
- 仕事算 (「一日の仕事量」×「日数」=全体仕事量 を思い出せることが重要)
- 割合と比の問題 (ものの個数、食塩水、売買損益の問題において、割合にあたる量を線分図として表現し、比の値を考えて計算結果を出す考え方を使う)
- 倍数と約数 (「最小公倍数、最大公約数」を、計算だけではなく「タイルをしきつめる問題」などを解くことによる「視覚的な理解」が重要)
- 時計算 (時計の針が進む様子を「点の移動」と捉え、短針と長針の進み方を「速さの比」と同一視して考えることが大事)
- 水量とグラフの問題 (問題文から「水面の高さ」を問われているのか、「水量」を問われているのかを把握しておくことが重要)
中学受験の算数の問題を解く上で重要なポイントは、以下のようなことが挙げられます。
- 問題文の「読み方」そのものを習得する。
- 与えられた条件や求めるものを把握した上で「どうすれば正解できたか」を思い出し、例題の解き方を「マネ」して正解できる力を習得する。
- 線分図や面積図を使って問題を解けるようにする。具体的には「~より多い」などの文章が問題文にあったら、その状況を線分の長さで表現できるようにする。
- 面積や多角形の角度などを求める際は、必要な公式や計算方法を思い出す。
- 計算ミスだけではなく「思い込みや勘違い」に注意する。「これは正三角形のはずだ」などの思い込みをしないようにする
- 見直しの仕方を習得する。「いつ、どこで、何を確かめれば良いのか」を、各問題ごとに把握しておく必要性がある。
- 上位校を狙う場合「自分で具体的な計算をしてみて、それを一般化させて答を出す」などの高度な力も必要。
中学受験の算数は「例題を題材として考え方を身に付け、その考え方を使えるようにする力」が重要です。
その中でも特に重要なのが、問題文を読み「線分図を描けば良いのか、面積図を描けば良いのか」を判断できる力です。
そうした力を身に付けられるようにするためにも、「同じ考え方で正解できる類題を繰り返し練習する」という姿勢が大事になります。
結論、中学受験の算数で大事なのは「発想力」などではなく、例題を通して身に付けられる「基礎学力」です。
受験に向けての算数の勉強方法や参考書の選び方
ここでは簡単に、中学受験の算数の勉強を進めていく上で重要なことについて書いていきます。
- 目標を明確にする:まず大事なのは、具体的に「どのような中学に行きたいのか」を明確にすることです。「偏差値帯でいうとどこなのか」「宗教校に行きたいのか」など、学校見学などにも積極的に行きながら決めていきましょう。
- 「基礎」の基準を明確にする:目標を明確にしつつ、行きたい中学が定まってきたら、今度は「その中学を目指す上で身に付けるべき基礎学力」の基準を明らかにしましょう。偏差値65の中学に行きたいのであれば「典型的な発展問題」を解ける力まで要求されるため、単純に「基礎ができればok」というわけではありません。「よくある難しい問題」を解ける力が基礎学力の基準になるからです。
- 例題を題材として「考え方」を身につける:基礎学力の基準が明らかになったら、それを身に付けるためにふさわしい「例題」を解くことができるようにしておく必要があります。例題の問題文を読み、解説を聞いたり読んだりする過程で「この解説は正しいかどうか」を判断していきながら、「どのように考えることがきっかけで正解できたのか」を探しましょう。そうすることで、どんな問題を解く際にも出てくる「共通のポイント (正解を出せたきっかけ、捉え方など) 」が見えてきます。
- 例題の「マネ」をする:「共通のポイント」が見つかったら、そのポイントこそが「考え方」ですので、「そのポイントを使って解ける問題は、他にあったかどうか」を振り返ってみましょう。もしあったのであれば「その問題はどのような問題文だったか」「問われていることは何だったか」を思い出して下さい。それを明らかにしておくことで、今度は「このような問題を解くときには、このポイントを使える」という仮定のもとで、実際に例題と似た問題 (類題) を「例題のマネをして、考え方を使って解く」という練習をしてみましょう。
- 何も見ないで「正解」を出す:「考え方」をマネして使いながら、「たまたま答が出た」という状態ではなく、「この考え方のおかげで正解できた」という一つの状態を目指して下さい。その際に大事なのは「解説・ヒントなど何も見ずに正解を出す」という姿勢です。解こうとしている問題の解説はもちろん「例題・他の問題の解説」なども、全て伏せておきましょう。そのような状況の中で実際に正解を出せてはじめて「考え方が身についた」「理解できた」と言えます。
- 問題を「ランダム」に解く:上に書いてきた一連の流れのもとで勉強できたら、今度は実際のテスト対策として「問題をランダムに解く」ということをして下さい。というのも、例えば「A」という例題があったとして、その次にA問題と同じ考え方で解ける「A’」という問題があったとします。同じように「B」という例題と「B’」という問題、「C」という例題と「C’」という問題もあるはずです。このとき大事なのは、A’~C’まで (あるいはもっと多くの問題) がランダムに与えられたときに「どの問題がA’で、どの問題がB’なのか」を正確に判断できることです。問題集には「A’、B’、C’、・・・」と書いてあっても、テストにはそのようなことは書いていませんよね (具体例でいうと、テストには「これは比例の問題です」などと書いていないはずです) 。大事なのは「これはB’問題です」と書いていなくても、自分で「これはこのような問題文だからB’問題」だと判断できた上で、実際にその問題に正解できることです。
- 「できること」を見つける:テスト対策とは、簡単にいうと上に書いたような「問題をランダムに解く練習のこと」です。このような意味でのテスト対策をしていきながら、間違いなく「これは絶対にできる」というものを見つけましょう。そうすることで「これができたら、次はこれも理解できる」という期待感を持つことができます。そうした期待感こそ、お子様のやる気につながります。
- 「間違い」の原因の特定:「できること」を見つけるのと同時に、間違ってしまった問題があれば「どこでどのような間違いをしてしまったのか」「どうすればその間違いをしなかったのか」を振り返りましょう。実際に「こうすれば間違えない」と思えるような仮定のもとに、その仮定が正しいかどうかを確かめるべく、再度間違えた問題と「その問題の類題」を解き直しましょう。解き直しの際に「ここでこんなことに注意しておく」という仮定が「実行できた上で、再度正解できたかどうか」を振り返って下さい。
参考書の選び方に関しては、上に書いたような勉強法を「実行できるような仕掛けがある書物」を選ぶことが重要です。
- 中受算数の基本は「予習シリーズ」一択!:まずそもそも「例題を題材として考え方を身につける」と書きましたが、中学受験の算数を理解するのに必要な考え方は「予習シリーズ」に集約されています。ここでは割愛しますが「予習シリーズ」とは、長年中学受験生のために愛用されてきた「中学受験生の必携書」ともいうべきテキストです。さまざまな問題集に手をつける前に、まずは「予習シリーズ」とその準拠問題集に掲載されている問題を、できるようにしておく必要があります。
- 各分野に特化した参考書を買う:予習シリーズを軸として「できるようにしておきたい問題」を明確にした上で、その問題が「どんな分野の、どの単元のものなのか」を把握して下さい。それを明らかにした上で、「その単元に特化した問題集」を選ぶのがおすすめです。理由は「強化したい単元だけに集中できるから」です。さまざまな問題が載っているものよりも「これだけ練習したい」と思える問題だけが載っていた方が、余計な知識に気を奪われずに済みます。
- 必ず「図での解説」が載っているものを選ぶ:「計算式だけで解説が済んでいるもの」を解答として載せている問題集・参考書はおすすめできません。中学受験の算数は、図形の問題はもちろん、文章問題も「必ず線分図・面積図」などの図に直せてはじめて理解できる問題ばかりです。このような理由から、必ず「図での解説」がされているタイプの書物を選んで下さい。
- 「例題」→「類題」→「練習問題」の順で問題が載っていること:先程の「考え方を身につけるプロセス」に沿って学ぶためにも、必ず「例題の次に、その例題のマネをしてできる類題」が載っている問題集を選びましょう。よく「問題のカタログにしかなっていない参考書」を見ます。それはつまり「この問題はこう解きます」という解説があったあとに「それとは別に、こんな問題はこんな解き方で解きます」という解説しか載っていないような書物です。そうした書物を利用してしまうと「この問題集にある問題は解ける (気になった) けど、それ以外の問題はできない」という状況に陥りやすいのです。そうならないためにも、「マネしてできる類題」が載っているものを選びましょう。
受験前に親が子どもととるべき受験対策とは?
受験前に親が子どもととるべき受験対策には、以下のようなものがあります。
まずは受験本番から逆算して、日々すべきことに関する計画を立てることが大切です。
試験日までのスケジュールを考え、その日に何をするか、どの科目に重点をおくかなどを決めましょう。
また、受験に必要な資料や教材を、志望校の説明会などにも足を運び、揃えておくことも忘れないようにしましょう。
受験直前期の話にはなってしまいますが、過去問題に取り組むことが、実は最も重要です。
過去問題を解くことで、出題傾向や難易度を把握し、受験に必要な知識や考え方を習得することができます。
また、必ず模擬試験を受けましょう。
SAPIXや四谷大塚などの大手の中学受験塾では、公開模試という形で、志望校判定テストなどを実施していますので、自分の志望校のレベルに合わせて、どの模試を受けるのかを計画して下さい。
そして何より、お子様の精神面のサポートが必要です。
中学受験はお子様にとって、精神面でも体力面でも負担がかかるものであるため、お子様の気持ちを理解し、適切にフォローすることが大切です。
十分な睡眠と食事を心がけることも忘れずに、健康な体と心を保つことが、受験に向けた最良の準備につながります。
子どもを勉強好きにする親の共通点とは?

「子どもが勉強好きになるにはどうすれば良いのか?」という悩みを抱える親御さんは多いことでしょう。
子どもが勉強に対して興味を持ち、自主的に学ぶ姿勢を身につけることは、長期的に彼らの学びや人生において大きな影響を与えることができます。
しかし、そのためには親御さんご自身がどのような姿勢でお子様の学びを支援するかが重要です。
このパートでは、お子様を勉強好きにする親御さんの共通点についてご紹介します。
親御さん自身が実践できる具体的な方法を学び、子供の学びを楽しく応援していきましょう。
子どもの興味や好奇心を大切にして算数との接点を見つける
お子様が算数嫌いになる原因として、学校での成績不振や苦手意識が挙げられますが、実はお子様の興味や好奇心を無視していることが根本的な原因であることも考えられます。
そのような状況にならないためにも、親御さんがお子様の興味や好奇心を大切にし、算数との接点を見つけることが重要です。
お子様が好きなスポーツやゲームなどを題材にした算数の問題を用意したり、身近な環境で算数に関連する問題を見つけて解いてみたりすることで、算数への興味を引き出すことができます。
お子様の好きなものから数量的なものを見出し、それに関連する分野の算数問題を提供することで、お子様の興味や好奇心を刺激することができます。
親御さんがお子様の興味や好奇心に寄り添い、楽しみながら算数を学ぶことができる環境を整えることが、算数の学習にとって非常に有効です。
子どもの自主性や自立心を尊重する
お子様を勉強好きにする親御さんの共通点の一つに、お子様の自主性や自立心を尊重することがあります。
お子様は自分自身で考え、問題を解決する力をそもそも持っています。
親御さんがお子様の代わりに「お子様自身ができること」まで全てのことをやってしまうと、お子様は自分で物事を考えることができず、勉強に対しても消極的になってしまうことがあります。
自分で考え、自分で解決することで、お子様は自信をつけ、勉強に対する意欲が高まります。
そのため親御さんは、お子様にもしできないことがあれば「どうすればできるようになるのか?」を一緒に考えられるように、自分自身で問題を解決する力を育むようなサポートすることが大切です。
子どもの学習状況や理解度を見守る
「自分自身で問題を解決する力」を身につけられるように、親御さんはお子様の学習状況や理解度を見守ることが大事です。
「学習状況を見守る」と書きましたが、親御さんから一方的に何かを教えるということではありません。
親御さんからお子様に対して「その日何を習ったか?」「何ができるようになったのか」を、お子様自身に話してもらうことが重要です。
そうした対話を経て「できていることは何か?」「できるようになりたいことは何か?」を把握し、適切なサポートを行うことが大切です。
お子様が学習において理解できないところがあれば「そもそも前に習った単元で、理解したつもりになっているところはないか」を把握して下さい。
そしてその上で「どこがわからないのか」「どのような点が不明確なのか」を明らかにしましょう。
また、お子様からの質問に対しては、どんなに些細なことだと感じても「そんなことはどうでも良い」などとは言わず、お子様が納得するまで、お子様の発言を聴くことが大事です。
お子様が学習に苦手意識を抱いてしまった場合には、それを否定せずに受け止め、一緒に乗り越えるためのアドバイスや支援を行うことも時には必要です。
学習状況を見守り、適切なサポートを行うことで、お子様が自信を持って学習に取り組めるようになり、勉強好きになることができます。
子どもが「説明する場面」を作る
「教育」というとどうしても、大人が「教える」「説明する」というものだと捉えられがちですが、実は逆で「子ども自身が説明する場面」を作ることが大切です。
この方法は、お子様自身が「自分の学んだこと」をまとめ、理解を深めることができるだけでなく、自信や自己肯定感を高めることもできます。
ただし「子どもの説明が正しいかどうか」を親御さんが確かめることも重要です。
親御さんからは、お子様の説明に対して適宜「質問」を投げかけ、お子様自身が「理解できていること」を認めてあげられるような場面を作れると良いでしょう。
親御さん自身が真剣に説明を聴き、お子様の思考過程を理解しようとすることが大切です。
こうすることで、お子様は自分の考えをまとめ、自分なりの言葉で表現する力を身に付けることができます。
お子様が自信を持って自分の考えを説明できるようになると、学習へのモチベーションが高まり、勉強が好きになることが期待できます。
子どもの努力や成果を認めて褒める
お子様を勉強好きにするためには、褒めることも大切です。
と言っても、ただただ「素晴らしい」「天才だね」などと言うのではなく「事実として、あなたは〇〇ができるようになっているよ!」というような声かけをすることが大事です。
結論からいうと「能力を良く言うこと」ではなくて「事実を伝えること」が大事です。
このことによって自信を持ち、より一層学習に励むようになることも期待できます。
褒めることには注意が必要で、お子様が簡単に達成できる目標に対して褒めると、子どもとしては「バカにされたような気持ち」になってしまうこともあります。
また、失敗や間違いをした場合でも、その努力や取り組みに対して「ここまでは良かったよ」と伝えることで、子どもたちは自己肯定感を高めることができます。
さらに、新しいことに挑戦していることに対しても「そんなことできないよ!」などではなく「成功する青写真」が見えるような声かけが重要です。
こうした褒め方をすることで、お子様は勉強を楽しんで継続することができ、自分の成長につながると感じるようになります。
子どもに適度な目標や期待を持たせる
お子様に対しては、まずは達成可能な適度な目標や期待を持たせることが大事です。
目標や期待は、それらを達成させることで、お子様が自分自身の成長を実感することや、やりがいを感じることができるようになります。
しかし、目標や期待が高すぎると、逆にプレッシャーになってしまい、お子様のやる気を削いでしまうこともあります。
そのため、お子様の性格や能力を考慮した上で「これを達成させたら次はこれ」「その次はそれ」という具合に、段階を重視した目標や期待を持たせることが大切です。
目標や期待を設定するときには、お子様自身が希望する方向性を尊重することも重要です。
また、目標や期待を持たせる際には、具体的な方法や行動計画も親子間で共有し、お子様が自分で考えた目標を達成するための道筋を示すことも大切です。
子どもが自ら答えを出すまで待つ
算数に限らず、お子様の勉強に対して、親御さんがすぐに答えを教えてしまうということをよく聞きます。
しかし、お子様に自分で考えさせ、自ら答えを導き出す時間を与えることが、算数の力を伸ばすためには重要です。
お子様が自分で答えを出すためには「自分の考えていることは正しいかどうか」を確かめながら「間違ったところはないかどうか」を見つけることが必要です。
親御さんがすぐに答えを教えてしまうと、上に書いたような意味でのお子様の思考力や判断力が育ちません。
そればかりか、すぐに答えを求めてしまい、自分で考える力を失ってしまうかもしれません。
もしお子様が「分からない」と言ってきたら、自ら答えを出せるようになるために、まずは問題文を音読してもらいましょう。
問題文において「何を問われているのか」を理解させるために、問題文を読んだ後に「何が求められているのか」「どのように考えればいいのか」といった質問を与えることが大切です。
このような対話を経て、自分で考えるための十分な時間を与えることが大切です。
答えを導き出せなかった場合でも、親がすぐに答えを教えずに、「どのように考えたか」「どこでつまづいたか」を共有し、お子様と一緒に考えることで、自己反省や理解力の向上につながります。
算数の勉強方法と教材選びの工夫

算数の勉強方法や教材選びには、どのような工夫が必要なのでしょうか?
ここでは、お子様が楽しく算数を学ぶことができるよう、勉強方法や教材選びについて考えていきます。
具体的には、どのような勉強方法が効果的なのか、どのような教材を選ぶべきなのか、そして、その教材をどのように活用するべきなのか、などについて解説していきます。
読み進めることで、お子様に合った算数の勉強方法や教材を選び、効果的に学習するためのヒントが得られることでしょう。
子どもが算数を好きになる方法
算数を嫌いなお子様にとっては「好きになること」自体が難しいこともありますが、例えば将来の夢に関係することを教えたりすることで、算数に興味や関心を持たせることができます。
また、算数がそもそも「できなくて嫌い」というお子様は、基礎学力が身に付いていないことが多いです。
算数は応用力や思考力が必要な教科と捉えられますが、その前提として「基礎学力」が大切です。
基礎学力とは大雑把な言い方をすると「どの問題集にも載っているようなよくある問題を正解できる力」のことです。
そうした意味での基礎ができないと、どんな問題も解くことができず、苦手意識や嫌悪感が強まります。
基礎を確実にマスターすることで、自信や達成感を得ることができ、算数を好きになるきっかけも増えます。
また、お子様がミスしても「こうすればミスしない」と思ってもらえるような声かけの工夫も必要です。
算数はミスをすると点数が下がりやすい教科ですが、ミスは学習の過程であって、結果ではありません。
ミスをしたら、その原因や改善策を考えて、次に活かすことが大切です。
ミスを恐れずにチャレンジする姿勢を育てることで、算数に対してのイメージも良いものに変化していきます。
基礎からしっかりと学習する方法
算数が本当に苦手で、受験ではなく小学校レベルのものから復習し直したいという方は、教科書準拠のドリルを利用するのも一つの手です。
ドリルには「同じ解き方でできる問題」がいくつも羅列して出題してありますので、基礎知識や計算方法から学びたい方にはおすすめです。
ドリルに載っている問題を解いたりすることで、算数の基礎を確実に身につけることができます。
学習アプリを使うという手もありますが、あくまでも「副教材」として利用することをおすすめします。
理由は、いくらデジタル化が進んでいるとはいえ、最終的には「ペーパーテストで、ヒントなど何も見ずに、自分の書く字で答案を作らなくてはいけないから」です。
学習アプリは、スマホやタブレットなどのデバイスで手軽に算数の基礎を学習することができますが、結局のところ学習アプリは「ボタンを押すだけのもの」でしかありません。
音声や動画などのメディアを使って算数の基礎を楽しく教えてくれたり、レベルに合わせて問題を出題してくれたりもしますが、実際に自分で字を書いて学習する大切さを忘れないで下さい。
算数が苦手なお子様にとって、基礎的なことであっても一度学んだだけでは忘れてしまいやすいものです。
忘れないためには、定期的に復習することが大切です。
復習することで、算数の基礎を定着させることができます。
計算力を身につける方法
ここでは簡単に「低学年・中学年・高学年」に分けて、それぞれの学年別に「計算力を身につけるために必要なこと」を説明します。
計算力を身につけるためには、当然「計算練習」は必要ですが、ここでは「どのような思考を前提として、計算練習が意味あるものになるのか」について解説します。
- 低学年:低学年のうちは「正解にものを数える」「興味のあることと数・図形を結びつける」ということが大事です。普段から身の周りにあるものに対して「何がいくつあるのか」を正しく把握できるようにしておきましょう。そうすることで「もの」に対して必ず「数」が対応することが分かり、足し算引き算の操作も理解できます。但し、足し算引き算を考えるときには「同じもの」を複数個扱うことが大事です。「みかん3個とりんご2個合わせていくつ?」ではなく「Aさんはみかんを3個、Bさんはみかんを2個持っているとき、みかんは全部で何個?」という問題を考えることが重要です。
- 中学年:中学年からは、足し算かけ算に加えて「割り算」を扱うことになります。このとき大事なのは、まずは「逆を考えられること」です。かけ算で「3×2」であれば「3を2回足すこと」を考えれば良かったのですが、中学年からは「2回足して6になる数は何か?」という考えに始まり、割り算を習得していくことになります。このような考えがあるからこそ「3回足して1になる数は1/3」「5回足して2になる数は2/5」という具合に、「分数」を理解できます。
- 高学年:高学年においては、中学年で学んだ「分数・小数」を基本として「単位量あたりいくらか」という考えを身につけていくことが最も重要です。中学年では割り算の文章問題を通して「1人何個もらえるか」「1個何円か」などの問題を考えますよね。高学年では割合や比を学び「100%にあたる量」「1に相当する量」を考えることになります。その際に「割り算で答が出るのか、かけ算で答が出るのか」を判断できることが大事です。このような観点からも、計算力を身につけるためには、ただ計算練習を繰り返すだけではなく、必ず文章題も扱うことが重要です。
親ができる算数学習サポート
お子様の算数学習をサポートするためには、親御さんがどのような方法で支援するかも重要です。
例えば、毎日の宿題やテスト勉強を見守ったり、お子様が困った問題について質問してきた時には、共に考えて解決することなども大切です。
重要なサポートとしては「その日何を学んだか」「できるようになったことは何か」をお子様に聞き、実際にお子様が親御さんの前で、問題に正解できる場面を作ることも大切です。
また、お子様の理解度や興味関心に合わせて、適切な教材を選ぶことも重要です。
お子様と一緒に「どんなレベルの教材なら算数の勉強を無理なくできるか」という視点も持った上で、教材を選びましょう。
こういった親御さんのサポートを通じて、お子様の算数学習がより効果的に進むようになるでしょう。
教材選びのポイントとおすすめ教材
教材選びのポイントについて再度、ここでお伝えします。
- 学習の目的別に選ぶ:算数の教材には、学校の授業の復習や苦手な分野の克服を目的としたものや、中学入試にも対応できるものなどがあります。自分の目標に合わせて、適切なレベルや内容の教材を選びましょう。
- 伸ばしたい能力別に選ぶ:算数の教材には、計算力や思考力、応用力などを伸ばせるものもあります。自分が強化したい能力に応じて、工夫された問題形式や解説量の教材を選びましょう。
- 「テストのページ」がある: 算数の成績を上げるには、問題演習だけではなく「テスト形式の学習」が必須です。つまり、問題をランダムに与えられたときに、「この問題は、あの単元のあの解き方で解ける問題だ!」という考えをアウトプットできるような仕掛けが、学習上必要です。
この3つの条件を満たす問題集を、いくつかご紹介します。
教科書ぴったりトレーニング (非受験生向け)
「算数が苦手」「まずは小学校のカラーテストで点数を取りたい」という方におすすめです。
各ページをコピーして、何度でも問題演習できるようにしておくのも良いのではないでしょうか。
分野別学習ノート (非受験生向け)
「これだけは理解に時間がかかる」という単元がある方におすすめです。
予習シリーズ (受験生向け)
中学受験をされる方は、四谷大塚・早稲田アカデミーなどに通うと必ず利用します。
予習シリーズには「中学受験に必要な基礎」が全て載っています。
偏差値55以上の中学を狙う方は必携です。
2人に1人が解ける基本問題 (受験生向け)
中学受験をされるお子様の中でも、偏差値50前後の中学を志望する方、あるいは「6年生から受験勉強をはじめたい方」などにおすすめです。
偏差値だけで中学受験の算数の問題を詳しくお伝えすることは不可能ですが、こちらは「偏差値50前後、合格倍率2未満の中学を受験される方の入門書」という扱いで良いでしょう。
中学入試よくでるランキング (受験生向け)
このシリーズは「図形編」もあります。
中学受験をされるお子様に「ここだけはどうしても苦手」という単元があるとき、6年生における学習の際にあると便利かと思います。
算数嫌いな子供に「もっと勉強しなさい!」と言ってはいけない?理由と対策
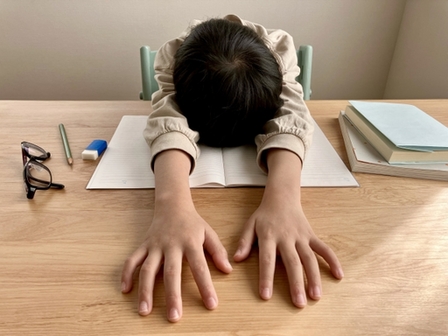
算数が苦手なお子様に対して、「もっと勉強しなさい!」と言ってしまう親御さんは少なくありません。
しかし、このような言葉は逆効果になり、お子様のモチベーションを下げてしまうこともあります。
そこで、本パートでは、算数嫌いなお子様に対して「もっと勉強しなさい!」と言ってはいけない理由と、対策についてご紹介します。
このパートを読むことで、算数嫌いなお子様をサポートする際に役立つ知識を得ることができます。
また、子供のモチベーションを上げ、楽しく算数を学ぶ方法についても学ぶことができます。
理由1. 子どもの自信ややる気を傷つける
算数が苦手なお子さんに「もっと勉強しなさい!」と言ってはいけない理由は、お子さんの自信ややる気を傷つけるからです。
子どもは、自分が苦手なことを言われると、ますます嫌いになってしまうことがあります。
また、努力しても結果が出ないと感じると、自信を失い、やる気が低下してしまいます。
お子様の努力や進歩に対しては、必ず褒めてあげましょう。
その上で、お子様自身が自分の成長を実感できるような目標を設定して、自分自身で努力し、達成感を得られるようにサポートすることが大切です。
理由2. 子どもの興味や関心をなくす
算数が苦手なお子様にとって、勉強することは辛く、やる気が起きなくなることがあります。
その原因の一つに、興味や関心を失ってしまうことが挙げられます。
算数の問題は、学年が上がるにつれて抽象的になり、現実との接点を見出しにくくなるため、お子様にとって興味深いものではなくなることも多いです。
また「この解き方しか通用しない」という問題も出てくるため、お子様が自分の思考力や創造力を発揮することができない場合もあります。
このような状況で、親御さんが無理に「子どもの知らなかった解き方」を強要したり、否定的な言葉をかけたりすると、お子様の興味や関心を完全になくすことにつながります。
親御さんがお子様の興味や関心に対して配慮し、興味を持てるような学習環境を整えることが重要です。
理由3. 子供の自主性や主体性を奪う
「勉強しなさい」と指示されることで、お子様の自主性や主体性を奪ってしまうことにつながります。
その結果、自己肯定感が低くなり、自信を失ってしまうことがあります。
指示されることが当然になってしまうと、お子様は自分自身で考える力や行動力が低下してしまいます。
そういった状況が続くと、お子様は「自分にはできない」と考えて、勉強に対して否定的な印象を持つことになります。
親御さんはお子様に選択肢を与え、自分から学ぶことを促すことで、自主性や主体性を引き出すことができます。
お子様の自主性や主体性を奪わないように、親がサポートすることで、子供の学習意欲を高め、積極的な姿勢を育てることができます。
対策1. 子どもの苦手なポイントや原因を見つける
子どもが算数で苦手意識を持ってしまう原因はさまざまですが、特に多いのは基本的な計算や数字の読み書きを間違ってしまうことなども挙げられます。
親御さんがお子様の苦手ポイントを見つけ、適切な対処をすることが大切です。
まずは、お子様がどのような問題で苦手意識を持っているのかを見極めることが必要です。
そのためには、お子様に計算や問題を解く過程を説明してもらい、どこでつまづいているのか (どんなミスをしたのか、勘違いしたままになっている箇所などの有無) を確認することが大切です。
次に、その苦手ポイントを克服するために、お子様に合わせた教材 (もっと言えば繰り返し問題演習すべき類題) や学習方法を選ぶことが必要です。
親御さんがお子様の苦手ポイントや原因を見つけ、適切な対処をすることで、お子様は自信を取り戻し、算数への苦手意識を克服することができます。
対策2. 子どもの得意な分野や好きなことを活かす
子どもが得意な分野や好きなことを活かすことは、勉強に対するモチベーションを高め、学習効果をアップさせることができます。
例えば、算数が苦手でも、音楽やスポーツで得意な分野がある場合は、その分野と算数を関連付けて学習することで、算数への興味を引き出すことができます。
また、好きな科目に取り組むことで、自信をつけることができます。
そのため、お子様の得意な分野や好きなことを活かすことができるよう、親御さんはお子様の興味や関心をよく観察し、学習に活かせるようなアイデアを提供することが大切です。
例えば、絵が得意なお子様には、算数の文章問題を絵に描いて解く方法を教えるなど、楽しく学べる工夫をしてみると良いでしょう。
対策3. 子どもの思考特性や理解できるまでのペースを把握する
子どもの学習において、重要なことの一つに「思考特性による個人差」があります。
ここでいう「思考特性」とは、子どもが本来持つ「ものごとの捉え方の傾向」とも言えます。
特に算数のように、前提知識が必要な分野では、理解度に大きなばらつきが出てきます。
親御さんがお子様の学習をサポートするためには、その差異を把握することが大切です。
お子様の思考特性や理解できるまでのペースを把握するには、まずはお子様が「どのように問題文を読んでいたのか」「図形をどう捉えているのか」などを観察することから始めます。
その上で、お子様が自分で問題を解く過程で「理解できていることは何か」「正しいと思い込んだまま間違いをしてしまっているポイントがないかどうか」を理解することが大切です。
例えば角度の問題であれば、お子様が根拠なしに「ここは90°だから~」という発言をするご様子などはありませんか?
このように「問題文にも、与えられた図にも書いていないことを、あたかも正しいことのように言う場面」がないかどうかを観察することが必要です。
親御さんがお子様の思考特性や理解度を把握することで、お子様が「算数を苦手にしてしまう原因」を見つけ、効果的な学習方法を導き出すことができます。
親御さんがお子様の学習をサポートするためには、お子様の個性も尊重し、適切なアプローチをすることが大切です。
勉強を教えるならリビング?それとも子ども部屋?

勉強を教える場所には、リビングや子ども部屋など様々な選択肢がありますが、どこが最適なのでしょうか?
親御さんにとって、お子様の勉強環境を整えることは重要な役割の一つです。
このパートでは、勉強を教える場所としてのリビングと子ども部屋について、それぞれのメリット・デメリットや適した場面を紹介します。
勉強環境を整える上でのポイントや、お子様の学習に適した空間づくりのアイデアなども提供します。
お子様にとって最適な勉強場所を見つけるためのヒントやアイデアを、このパートでは提案します。
ご自宅でお子様の勉強を考えている親御さんにとっては、勉強のための空間づくりの参考になるでしょう。
リビングで教えるメリット
リビングで勉強を教えることにはいくつかのメリットがあります。
まず、リビングは家族が集まる場所であり、子どもが勉強するための集中力を高めるのに最適な環境を整えることができます。
また、お子様からの相談事があった場合には、すぐに応えることができるため、「悩み事をそのままにしない」という意味で、学習効率を高めることができます。
さらに、リビングで勉強することにより、家族とのコミュニケーションが増え、家族との絆を深めることもできます。
家族で協力して勉強することで、お子様の勉強に対しての意欲を高めることもできます。
リビングで勉強を教えることには、家族の絆を深めることや、学習効率を高めることなど、様々なメリットがあると言えます。
- 親御さんがお子様の学習状況や理解度を把握しやすい
- 子どもが質問や相談しやすい
- 子どもが集中力や自制心を身につけやすい
リビングで教えるデメリット
リビングで勉強を教えることには、いくつかのデメリットもあります。
- 兄弟などがいる場合は、集中力が散漫になる可能性がある。様々な音や動きがあるため、なるべく一人になりたいタイプのお子様にとっては、勉強に集中するのが難しいこともある。
- 勉強環境が整っていない:リビングにテレビやゲーム機など、気晴らしになるものがたくさんある場合、勉強に集中しにくくなってしまう。
- 子どもがリラックスしすぎる:リビングは家族が集まる場所であり、くつろげる空間でもあるため、お子様にとって「リラックスする場所」として認識されている場合、勉強に集中できない。
これらのデメリットを克服するためには、リビングでの勉強にはルールを設けることが必要です。
勉強中は静かにする、テレビやゲーム機は使わない、などのルールを設け、お子様が勉強に集中できるよう、環境を整える必要があります。
子ども部屋で教えるメリット
子ども部屋で勉強を教えるメリットとしては、お子様が自分のスペースで学習に集中しやすくなることが挙げられます。
子ども部屋には自分専用の机や椅子、本棚や学習グッズなどが揃っていることが多く、その空間にいるだけで勉強する意欲が湧いてきます。
また、リビングなどの共用スペースで勉強する場合には、家族やペット、テレビや音楽などの外部刺激が集中力を乱す可能性があるため、子ども部屋の方が静かな環境が整っていることも多いです。
子ども部屋での勉強は、お子様が自分のペースで進めることに適しているため、ストレスを感じずに自分の理解度に合わせた勉強ができます。
- 子どもが自分のペースや方法で学習できる
- 子どもが自分の机や棚などを自由に使える
子ども部屋で教えるデメリット
子ども部屋が散らかっている場合、子ども部屋ではそもそも勉強に集中できない場合もあります。
教材や文具などが勉強机の上に乱雑になっていると、お子様は集中することができず、学習効果が低下する可能性があります。
また、子ども部屋にお子様と親御さんだけが「1対1」の状態になってしまうと、お子様は常に監視されているような気持ちになってしまう懸念もあります。
また、リビングではなく子ども部屋にゲーム機などがある場合、そもそもその部屋は勉強に向きません。
これらの理由から、子ども部屋での勉強をする場合は、教材や学習環境を整えることが大切です。
- そもそも部屋が散らかっていると集中できない
- 親が常に子どもを監視しているような状態になる
- 子どもがゲームや漫画などに手を出してしまう
勉強を教える際には親御さんの考えだけではなく、お子様の考えや意見も聞いて、親子間で話し合った上で一緒に決めていくことが大事です。
まとめ
もともと算数が苦手だった親御さんでも、お子様に対して「算数の苦手意識を克服できるような教え方」で算数を教えることは可能です。
教え方のポイントは以下の通りです。
- お子様が苦手意識を持つ理由を理解することが重要です。具体的には、過去の経験や周りの環境が影響していることなどもあります。
- お子様が苦手意識を持つと、自信を失い、学習意欲が低下するため、積極的にサポートする必要があります。
- 算数が苦手なお子様に対して、焦らずゆっくりと1つ1つの問題に向き合い、理解できるまで丁寧に説明することが必要です。
- 質問に対して否定的な返答をするのではなく、適切なフィードバックを行い、ポジティブな姿勢を持つことが大切です。
- 教材については、学校の教科書や参考書、オンライン学習サイトなど、お子様が理解しやすいものを選ぶことが重要です。
- リラックスした雰囲気で学習することができるように、お子様とのコミュニケーションを大切にしましょう。教材以外にも、算数が日常生活でどのように使われるかを身近な例で説明することも効果的です。
算数が苦手なお子様は、焦らずゆっくりと勉強を進め、適切な教材を選び、ポジティブな姿勢で取り組んでいくことで、苦手意識もなくなります。
[…] 算数を教えられない親御さん必見!子供の苦手を克服する教え方 […]