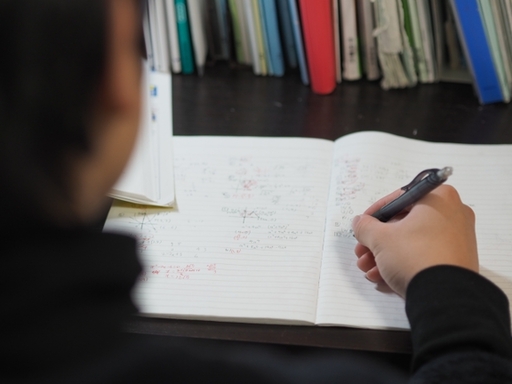算数や数学の勉強で、問題を解いたあと「すぐに答えと解説を見てしまう」という人は多いのではないでしょうか。
しかし実はその行動、「成績が上がらない勉強法」になっている可能性があります。
丸つけをする前に少し立ち止まって“自分の考え方”を振り返ることで、理解力・思考力・定着率が大きく変わります。
この記事では、「丸つけ前にやるべき正しい勉強の順番」を具体的に紹介します。
丸つけをする前に考える時間をつくろう
答えを見る前にまず行ってほしいのが、「自分の考えを振り返る時間」を取ることです。
たとえ答えが合っていても、「そもそも正解できたきっかけ」を言葉にできなければ、理解は浅いままです。
チェックしてほしい3つのポイント
- どこで迷ったのかを思い出す
→ 途中で止まった理由を言語化することで思考のクセが見えます。 - 自分の立てた式が正しい根拠を持っているか
→ 「なんとなく」ではなく、「こうだからこう」と説明できるか確認。 - 自分で説明できるか
→ 口に出して説明できるなら、その単元は“理解できた”状態です。
このステップを踏むことで、「理解して定着する勉強法」を身につけることができます。
すぐに答えを見る勉強法がNGな理由
丸つけ前に答えを見てしまうと、「見直しのプロセスを放棄する」ことになります。
「解けた・解けなかった」という結果だけに目が向き、次に同じような問題が出ても自力で解けなくなるケースが多いのです。
答えだけを見て“わかった気”になってしまうと、「本当は間違いなのに、正解したつもり」になってしまう部分が出てくる可能性も高くなります。
これが「復習しても点が伸びない」「同じミスを繰り返す」原因のひとつです。
正しい丸つけの順番とは?
丸つけは「自分で解答を検証する作業」として行うのが正しいやり方です。
- まず、自分で答え合わせを想定して確認する
→ 「この答えは本当に正しいかな?」と自分で検証。 - それから答えを見る
→ 正解と照らし合わせて“どこでズレたか”を明確にする。 - 最後に解説を読む
→ 「どうしてこの考え方が正しいのか」を理解し、再現できるようにする。
この順番を守ることで、「自分で考えて→検証して→納得する」という理想的な学習サイクルが完成します。
保護者ができるサポートのコツ
家庭学習で丸つけをするとき、親ができるサポートもあります。
すぐに答えを見せるのではなく、「自分で考えた部分を話してもらう」時間をつくりましょう。
- 「どこまで自信ある?」
- 「どうしてそう思ったの?」
- 「他の方法もあるかな?」
こうした声かけで、子どもは“自分の考えを整理する力”を伸ばしていきます。
丸つけを「ただの採点」ではなく、思考力を育てる対話の時間に変えるのが理想です。
よくある質問
Q1. 間違えた問題はすぐに解説を読んでもいい?
→ いいえ。まずは「なぜ間違えたのか」を自分で探すことが大切です。理由を見つけてから解説を読むと、理解の深さがまったく違います。
Q2. 時間がないときはどうすればいい?
→ すべての問題でなくても大丈夫です。1日1問だけでも“自分で確かめる習慣”を持ちましょう。
Q3. 丸つけを親がしてもいい?
→ はい。ただし、子どもが自分で振り返る時間を取ってから丸つけするようにしましょう。
まとめ
丸つけをする前にすぐ答えを見る勉強法は、一見効率的に見えても「考える力を奪う勉強」になってしまいます。
正しい順番は、
①自分で振り返る → ②答えと照らす → ③解説で理解を深める。
この3ステップを習慣化することで、勉強の質は確実に上がり、テストでも“考えて解く力”が身につきます。